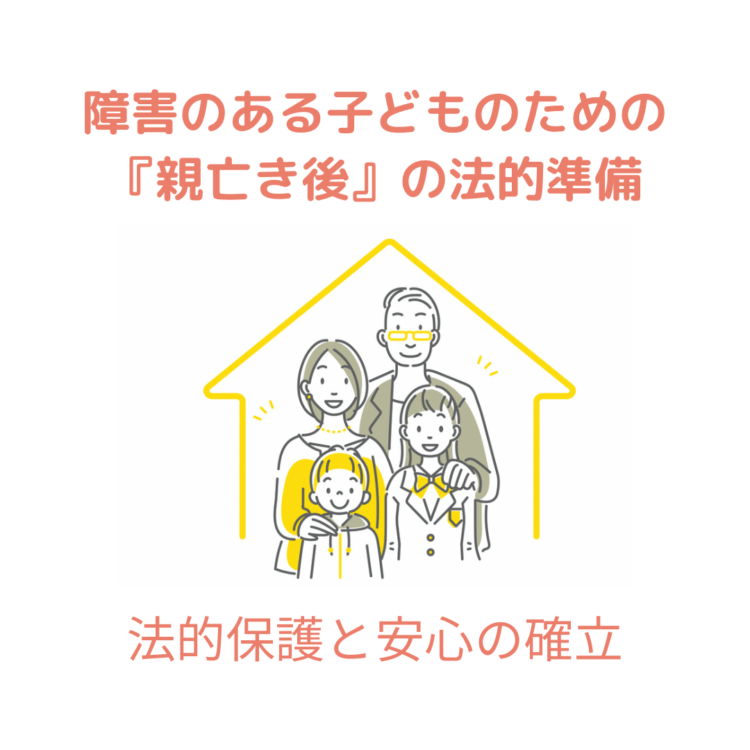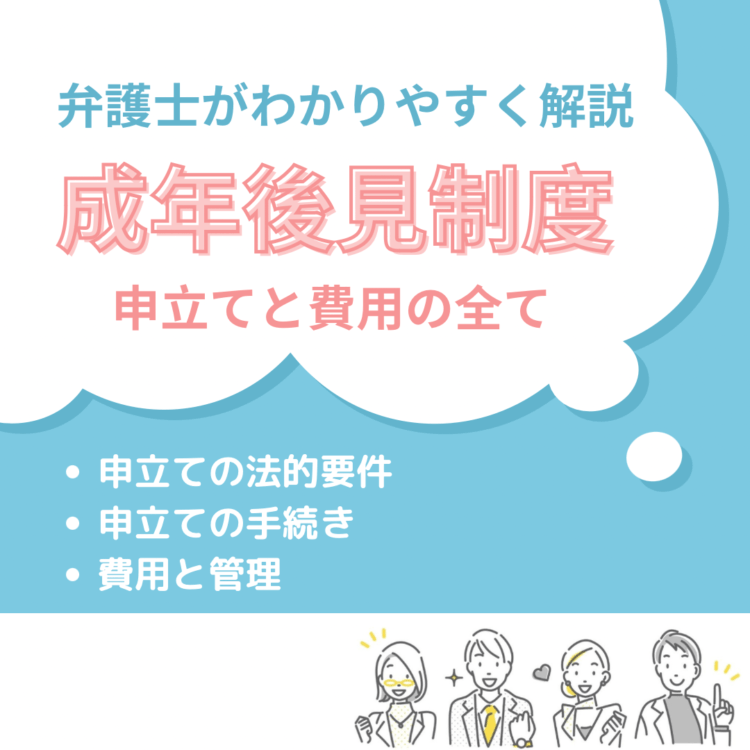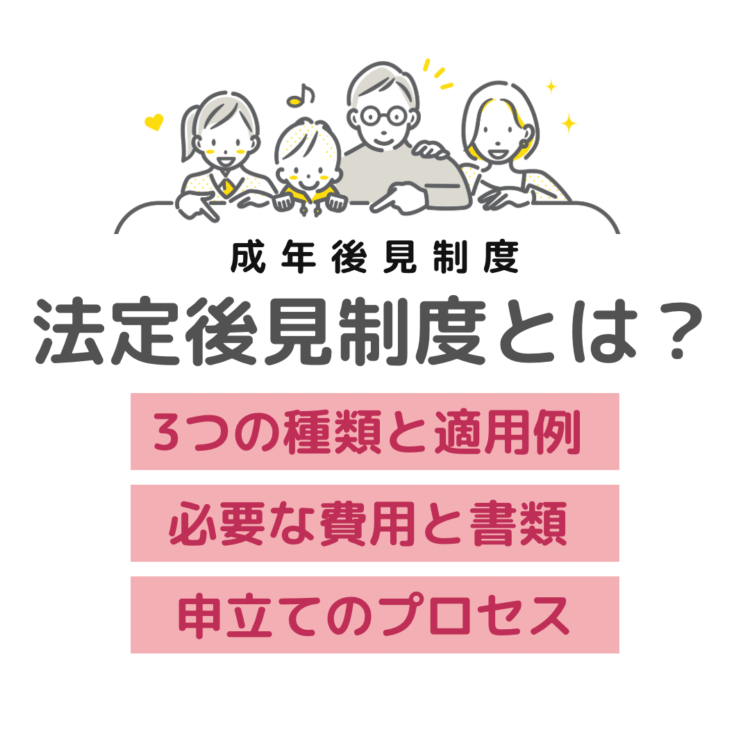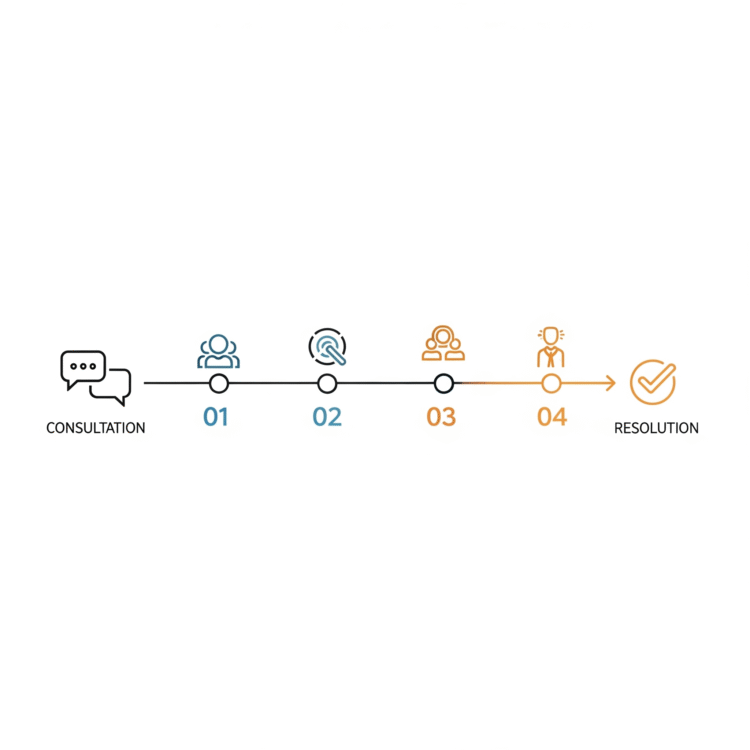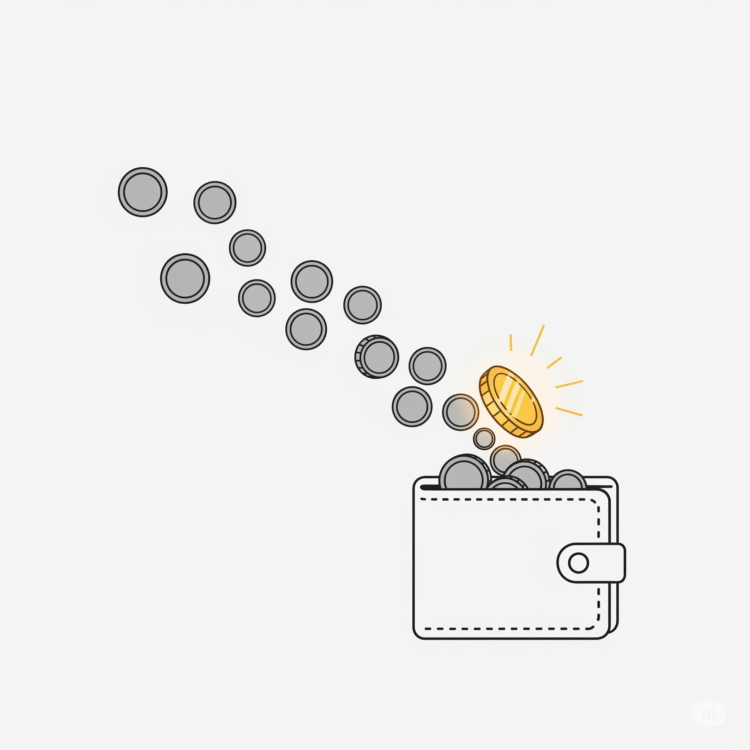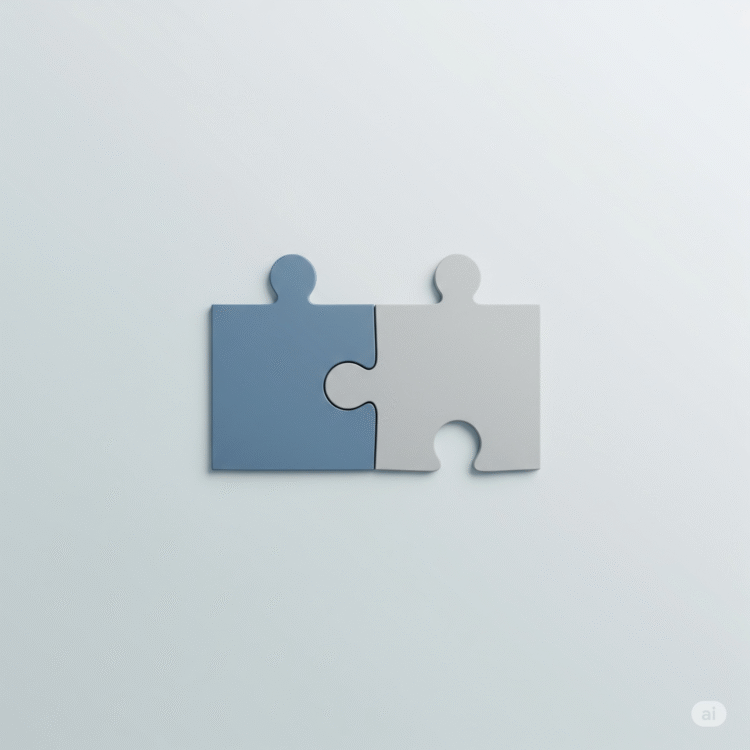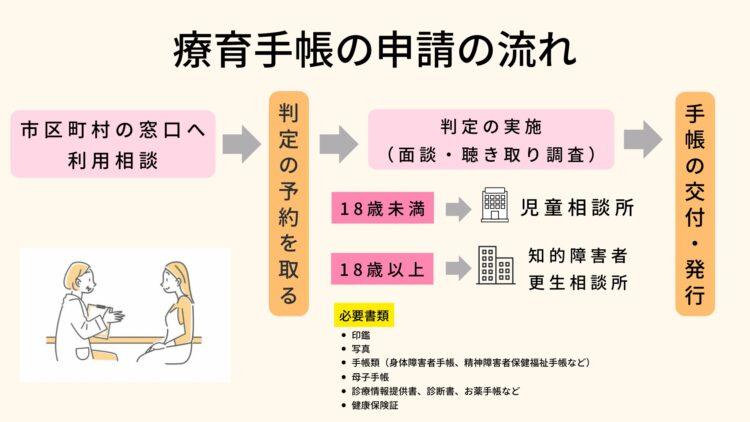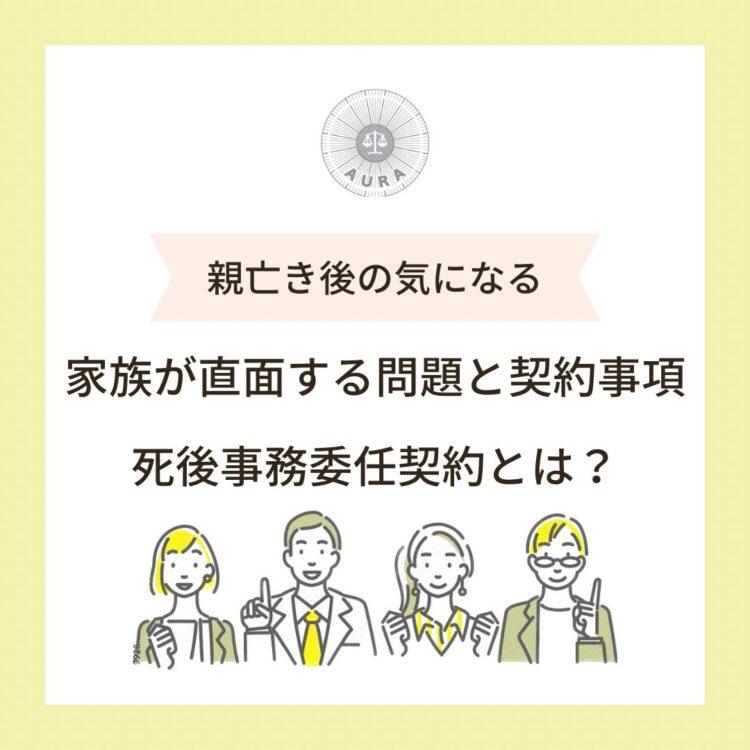目次
遺言執行者による遺言執行に抵触する相続人の処分
遺言執行者の選任
遺言の執行のために遺言執行者が選任されることがあります。必須というわけではありません。遺言執行者が選任されないこともよくあります。
遺言執行者が選任された場合,遺言執行者による業務の執行は強く保護されます。遺言の執行に抵触する行為があっても無効とされるのです。
遺言執行者の執行に抵触する行為
遺言執行者が選任されている場合,「遺言の執行を妨げるべき行為」はできず,遺言の執行に抵触する行為は無効となります。
対抗関係になるわけではなく,抵触行為により遺産を取得した者が登記を経ていても優先されません。登記を得ていても遺言内容に反していると無効となるのです。
そもそも登記があると優先されるのは対抗関係が成立している時です。対抗関係ではない場合は,登記があっても守られないのです。
具体例
① 相続人の処分行為
〈事案〉
相続人が相続財産に根抵当権を設定したが,これは遺言内容(遺贈)と抵触するものだった。
→根抵当権者が競売を申し立てた。
〈裁判所の判断〉
根抵当権の設定は無効であり,競売の申立ても無効である。
※最高裁昭和62年4月23日
② 相続人の債権者による差押
〈事案〉
法定相続人の債権者が相続財産を差し押さえたが,これは遺言内容(遺贈)と抵触するものであった。
〈裁判所の判断〉
差押は無効である。
※仙台高裁昭和63年3月22日
遺言執行者の就任時期と抵触行為の無効の関係
遺言の中に遺言執行者の選任が記載されていれば,結論としては抵触行為のタイミングに関係なく無効となります。選任の時期と遺産処分の時期の前後関係は,処分の効果に影響がないということ
相続人申立による遺言執行者の就任の時期と抵触の判断
遺言には遺言執行者の選任が記載されていないこともあります。この場合でも,相続人が家裁に遺言執行者の選任を申し立てることができます。
その後,遺言執行者が就任した時点から,抵触行為が無効になる期間がスタートします。遺言執行者が就任される『前』に相続人が遺産を処分した場合,この処分は有効です。
したがって,相続人が遺言と抵触する処分をしてしまうかもしれないというケースでは,他の相続人は急いで遺言執行者の選任の申立をして抵触行為として無効とする機能をオンにすべきです。
遺言執行に抵触する譲渡後の譲受人(転得者)
抵触行為の後にさらに別人に譲渡されることもあります。
〈第1取引(抵触する行為)〉
相続人Aが遺産の不動産を第三者Bに譲渡(売却)したが,これは遺言執行に抵触するものであった。
→譲渡は無効であるためBは所有権を取得しない。
〈第2取引(譲渡)〉
BはC(転得者)に不動産を譲渡(売却)した。
→転得者Cは所有権を承継しない。
転得者Cが所有権移転登記を得ていても,登記に公信力はない(登記の取得によって保護されない)ので,権利を取得するわけではありません。転得者Cは実質的無権利です。
転得者Cは民法177条の第三者に該当せず,対抗関係は生じません。
〈復元のための請求〉
遺言執行者は,登記抹消請求と不動産の引渡請求をすることができる。

生前処分と遺言の抵触
① 権利の帰属
売却や贈与などの生前処分と遺言の内容が抵触することがあります。例えば同じ財産について,贈与を受けた者(受贈者)と遺贈を受けた者(受遺者)が存在するようなケースです。
この場合,生前処分と遺言作成の時期の前後や登記の有無で最終的に権利を取得する者が違ってきます。
② 生前処分vs相続人(生前処分が優先となる)
相続の基本的な理論は,相続人が被相続人の地位をまるごと承継(包括承継)する,言い換えれば,遺言者(=譲渡などの処分をした者)の立場を相続人がそのまま引き受けるというものです。
したがって,相続人は財産を渡す立場にあるので,生前処分を受けた者に劣後する(=生前処分を受けた者が相続人に優先する)という関係にあります。生前処分を受けた者が財産を承継できるのです。
相続人については,遺言で承継する財産が指定されていても(遺産分割方法の指定),常に劣後となります。
③ 遺言作成(遺贈)→生前処分(遺言の撤回)
遺言を作成した後に贈与などの(生前)処分をしたケースでは,遺言の撤回に該当します。遺言の効力がなくなるので,結果的に生前処分の効力が生じるだけになります。
④ 生前処分→特定遺贈(対抗関係)
生前処分の後に遺言の作成がなされたケースを考えます。
不動産をAに贈与(や売却)した後に「不動産をAに遺贈する」という遺言が作成されたということを想定します。特定の財産を遺贈することを特定遺贈といいます。
遺贈の目的となる財産が相続開始時に被相続人に属しないことになるので,遺贈は無効となるように思えますが,二重譲渡と同じ状況として対抗関係に立つという判例の判断が確立しています。登記を先に得た方が優先される(対抗要件(登記)の順序で優劣が決まる)ことになります。
遺言執行者が選任されていても生前処分が劣後(無効)となるわけではありません。
⑤ 生前処分→包括遺贈(対抗関係)
生前処分の後に遺言が作成され,その遺言の内容が「遺産すべてを甲に遺贈する。」という財産を特定しない遺贈(包括遺贈)であったケースを考えます。
この点,包括遺贈の受遺者は相続人と同じ扱いをするという民法の規定(民法990条)があります。しかし,特定遺贈と同じ二重譲渡として対抗関係として扱うという見解が有力です。最高裁判例はありませんが,下級審裁判例もあり,実務では一般的な見解となっています。
その他、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。