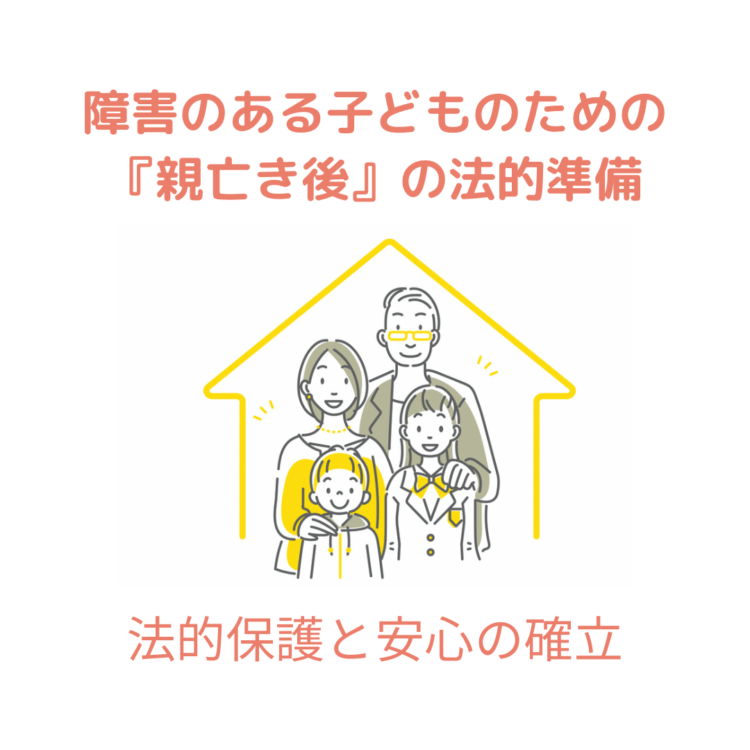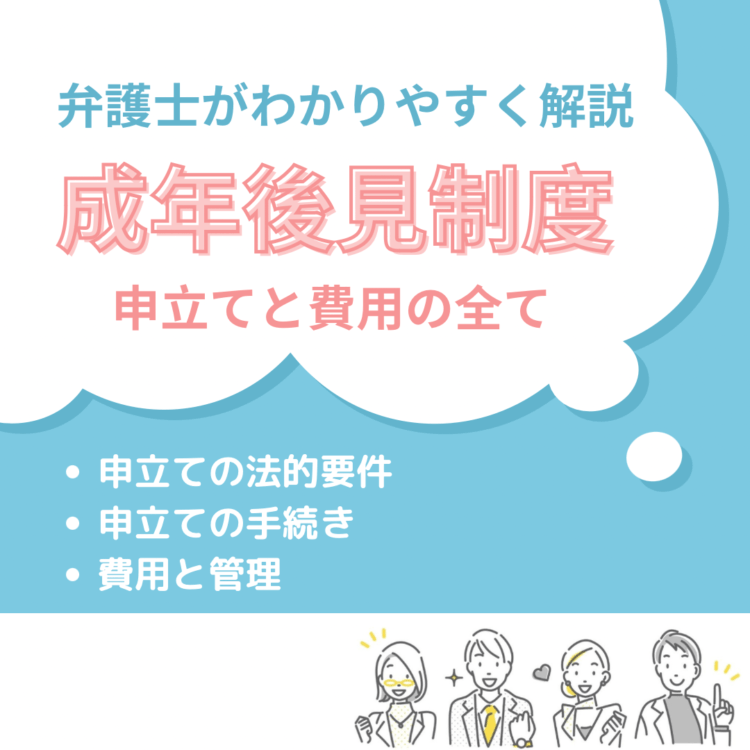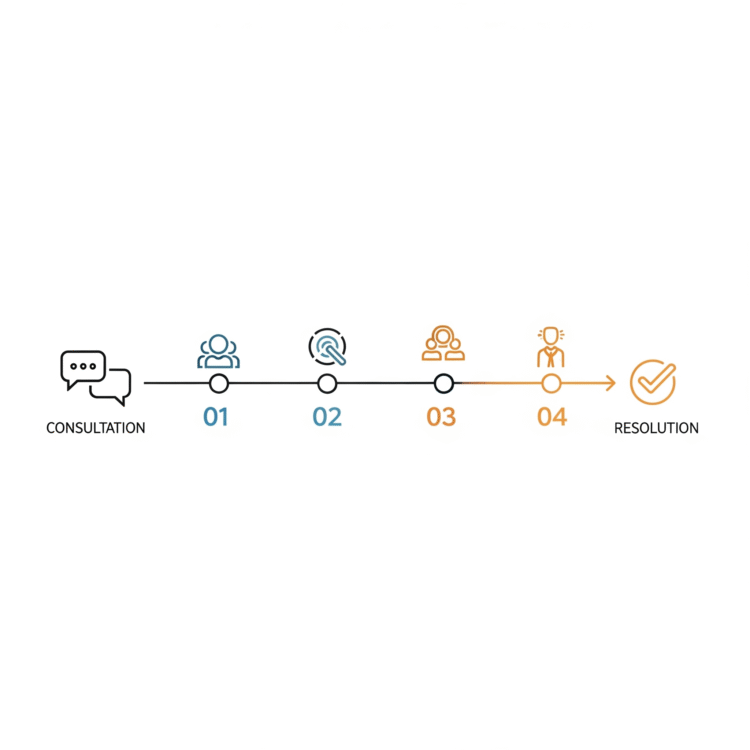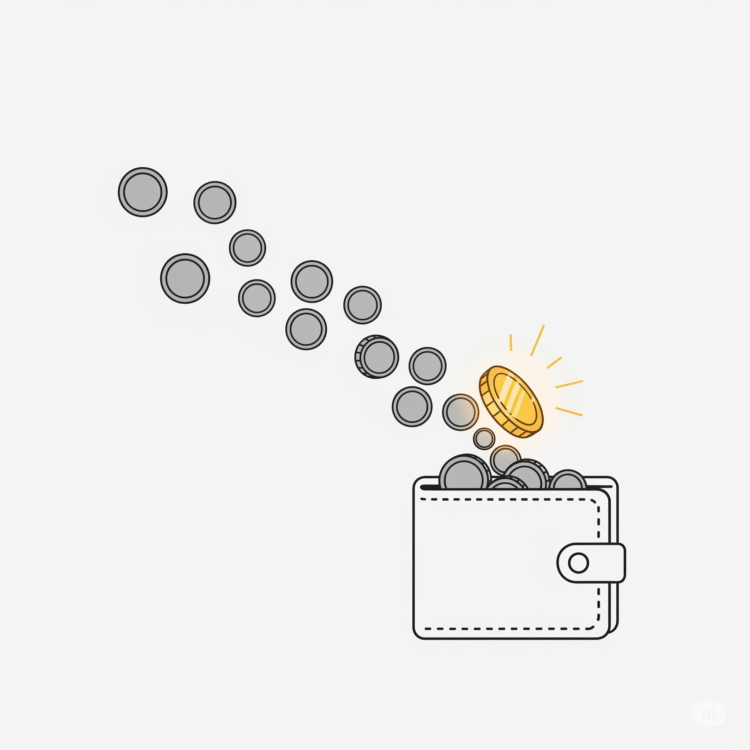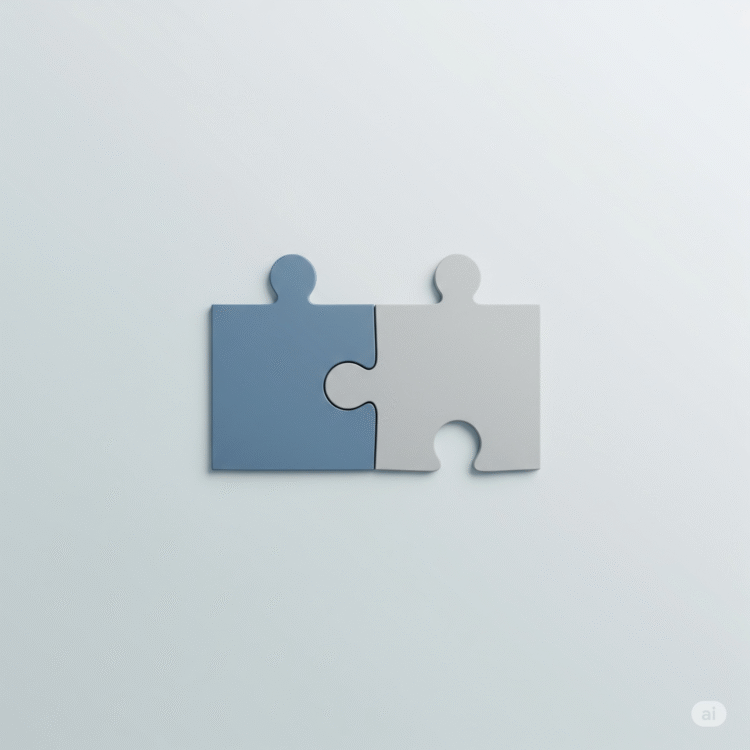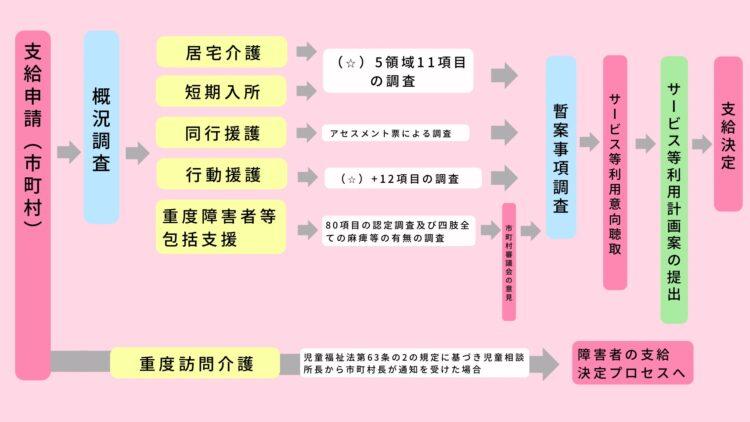目次
熟慮期間
被相続人が亡くなった後に,相続人が相続放棄又は限定承認を選択する際には,「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。
相続放棄・限定承認をせずに熟慮期間が満了した場合,単純承認をしたとみなされますが,事情によってはこの期間では相続放棄又は限定承認の選択をすることができないということもあります。
そこで,判例の解釈で,熟慮期間はある程度柔軟な扱いが認められています。
熟慮期間の起算点の原則的解釈
熟慮期間は,条文上「相続の開始があったことを知った時」(起算点)からカウントすることになっています。
被相続人が亡くなったという事実を知るだけでなく,自己が相続人となったことを知ることという要件が追加されています。
熟慮期間の起算点の繰り下げ
〈判例〉
熟慮期間の起算点について,上記2のような基準では,救済として不十分といえる状況があります。そこで,次のような最高裁判例が出されました。
「相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しりうべかりし時から起算するのが相当である。」(最高裁昭和59年4月27日)
相当な理由は,被相続人の生活歴,被相続人と相続人との間の交際状況,その他諸般の事情から総合的に判断することになります。
〈相続財産が全く存在しないと誤信する場合〉
相続財産がまったく存在しないと誤信する場合の解釈については,判例の文言どおりに解釈する見解(限定説)と,積極財産は知っていたがそれを超える消極財産は存在しないと認識していた場合を含むとする見解(非限定説)があり,多くの裁判例では非限定説が採用されています。非限定説の理由は,次のとおりです。
・積極財産がまったく存在しないということは常識的にあり得ないから,限定説はあり得ない事態を要件としており,不合理である。
・積極財産の一部を認識していても,相続債務はないものと誤信してた相続人は,限定説だと保護されないことになり,救済として不十分である。
明白性の基準プラス非限定説
〈明白性基準〉
相続放棄の申述は家庭裁判所の審判で受理するかどうかを判断しますが,その手続で,裁判所はどこまで事情を調査して審査するのかという問題があります。
相続放棄の要件の有無について入念な審査をすることは予定されていません。
受理した場合でも,実体要件を満たしていることが確定するわけではなく,相続放棄の効力が確定することはありません。
そのため,最小限の審査しかしない運用となっており,明白に要件を欠く場合でない限り受理することになっています。要件の欠缺が明白である場合にのみ申述は却下されます。
熟慮期間の繰り下げが認められる可能性があると,熟慮期間を経過していることが明白であるとはいえないとして,相続放棄の申述を受理するのです。
これを明白性基準と呼んでいます。
〈明白性基準を使った具体的な判断の方法〉
申立人の主張(要件を満たす主張)だけでは受理しませんが,かといって,一般の訴訟のようなしっかりした証拠が必要というわけではありません。最小限の証拠(受理を可能とする一応の証拠)で申述を受理するということです。
熟慮期間の起算点に問題がある場合には,後日の民事訴訟で決着させるという運用がなされています。家庭裁判所が相続放棄の申述を認めても,相続放棄の効果が確定するというわけではありません。別の民事訴訟で相続放棄の効果が認められるかどうかは別問題なのです。

裁判例
裁判例の多くは,非限定説の解釈だけではなく明白性基準も使って,より弾力的な運用をしています。
① 不動産の認識
相続人が相続財産に不動産が含まれていることを認識していたケースです。
不動産は一般的に高額な財産なので,相続財産が存在するという認識は明白であるとして,熟慮期間の延長を認めず,相続放棄の申述受理を認めませんでした。
ただし,不動産が相続財産に含まれることを相続人が知っていても,熟慮期間の繰り下げを認めるケースもあります(仙台高裁平成元年9月1日判決)。
※上記裁判例は,相続人Aは相続財産に不動産が含まれることを認識していたが,その不動産を長男Bが取得するもので,自分が取得することはないと信じており,かつ,Aは,被相続人には債務がないと信じていたケースで,Aは,債権者から請求を受けて初めて債務の存在を知った可能性があることから,Aがそのように信じたとしても無理からぬ事情がうかがわれるとして,熟慮期間の繰り下げが認められる可能性があり,熟慮期間を経過していることが明白であるとはいえないとして,相続放棄の申述を認めました。
② 債務完済の誤信
相続人が,相続財産として債務(マイナス財産)が存在することを知っていた場合,一般的には熟慮期間の繰り下げは適用されない傾向があります。
しかし,被相続人や他の関係者から受けた説明が原因で誤解した場合には,救済的に熟慮期間の繰り下げが認められる可能性があると判断し,相続放棄の申述を受理した裁判例があります。
この事案は,C銀行に対する債務について,相続人Aは,被相続人が債務を負担していたことは知っていたが,被相続人から債務額を聞いておらず,「債務を返済する必要がない。」旨聞いていたため,被相続人の死後,債務が残っているとは考えていなかったというケースです。
③ 抵当不動産売却による完済という誤信
相続人A・Bは,被相続人が漁協に債務を負担していたことは知っていた
被相続人の廃業時の減船の補償金が返済に充てられたと聞いていた
残債務はBの夫が不動産甲を担保に提供して負担することになったと理解していた
不動産甲が処分されて返済に充てられた
被相続人の債務が残っているものとは考えていなかった
④ 残債務の認識(仙台高裁平成8年12月4日)
残債務については,Bの夫が一切を負担することになったものと誤解していたため,C銀行・漁協から連絡を受けて調査するまで,A・Bは債務が債務が完済されたものとは認識していなかった。
被相続人の死亡当時,被相続人の債務として残っているものとは考えていなかった。
熟慮期間の繰り下げが認められる可能性がある。
熟慮期間を経過していることが明白であるとはいえない。
→相続放棄の申述を認めた
⑤ 借地権相続の誤認(東京高裁平成22年8月10日)
被相続人は借地人であった。
相続人が借地権の相続を認識していなかったと主張し,地主は通知や会話で借地権の相続を相続人に伝えたと主張したケースです。
裁判所は,通知の方法や供述の信用性から地主の主張を排斥し,相続人が借地権の相続を知っていたことが明白とはいえないから,熟慮期間の繰り下げの可能性があると判断し,相続放棄の申述を認めました。
⑥ 最近の裁判例(東京高裁平成26年3月27日)
共同相続人Aは,相続開始時に相続財産(特に積極財産)について認識していた。
しかし,自分自身には相続するべき財産はないと考えていた。
実際に積極財産の取得をしていない。
→Aは,相続財産が存在しないと信じていたので,Aが消極財産について積極的な調査をする期待可能性に欠ける。
→熟慮期間の繰り下げが認められる可能性がある。
→熟慮期間を経過していることが明白であるとはいえない。
→相続放棄の申述受理を認めた。
その他、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。