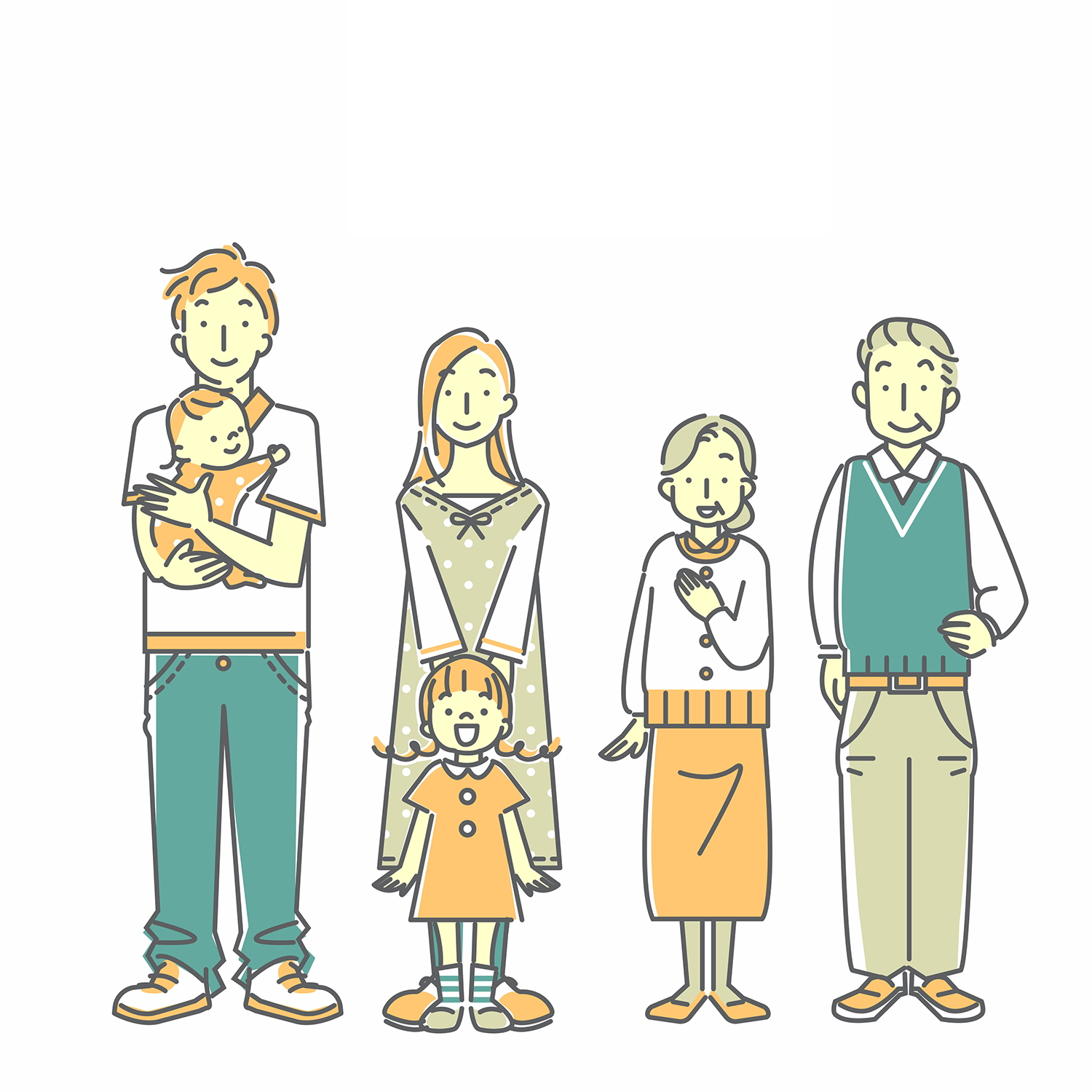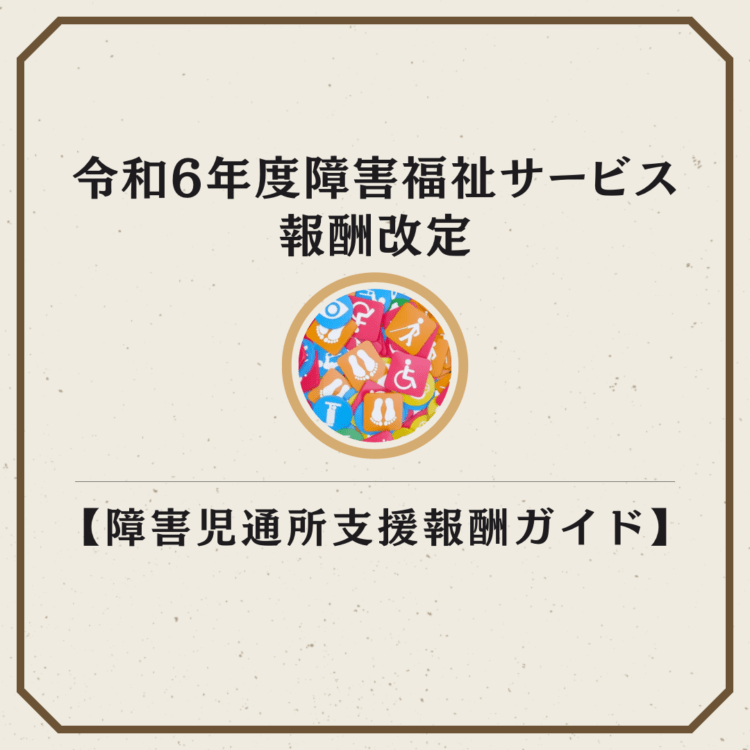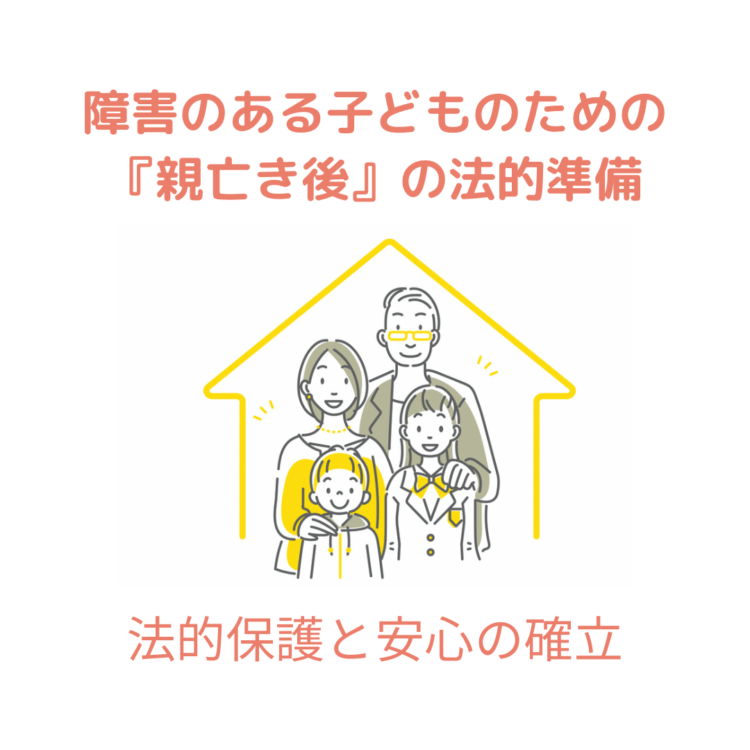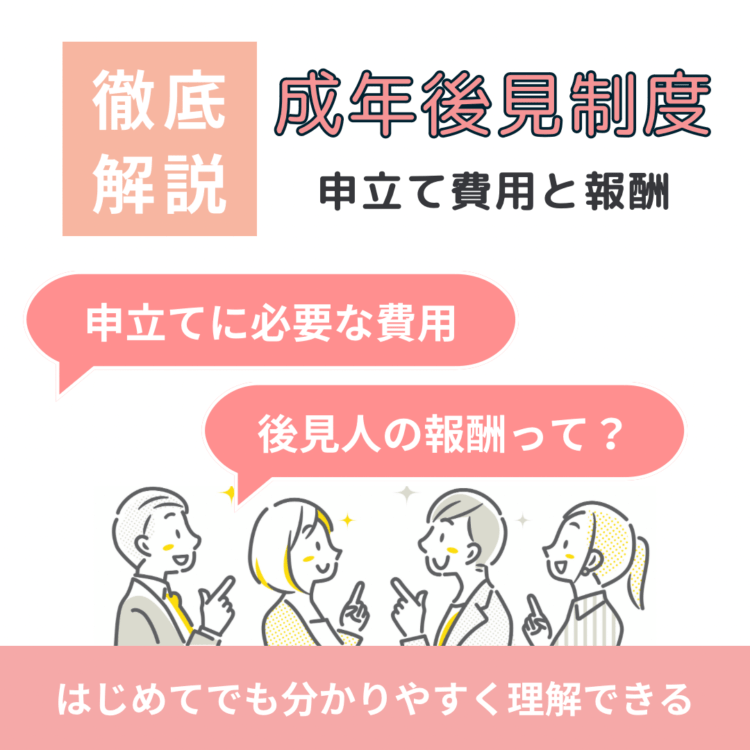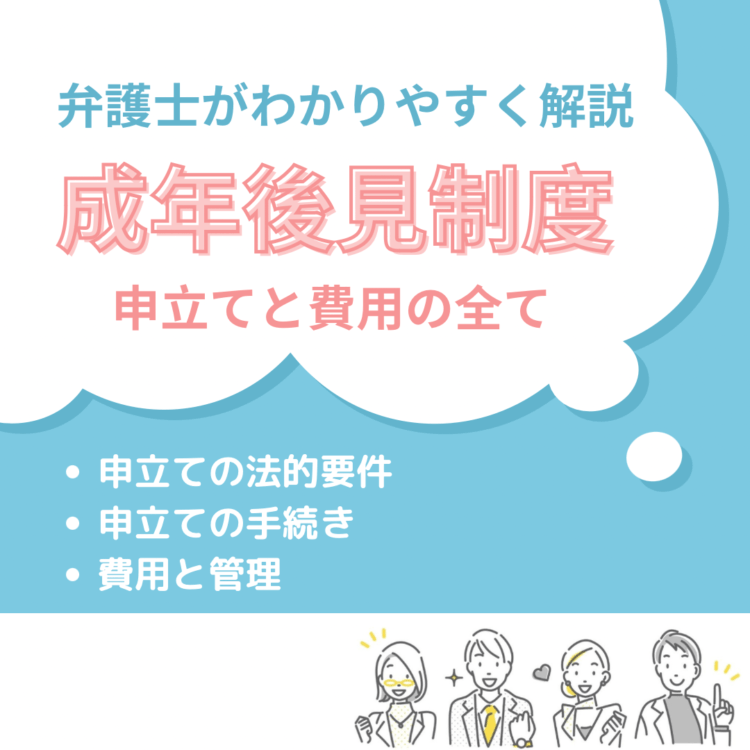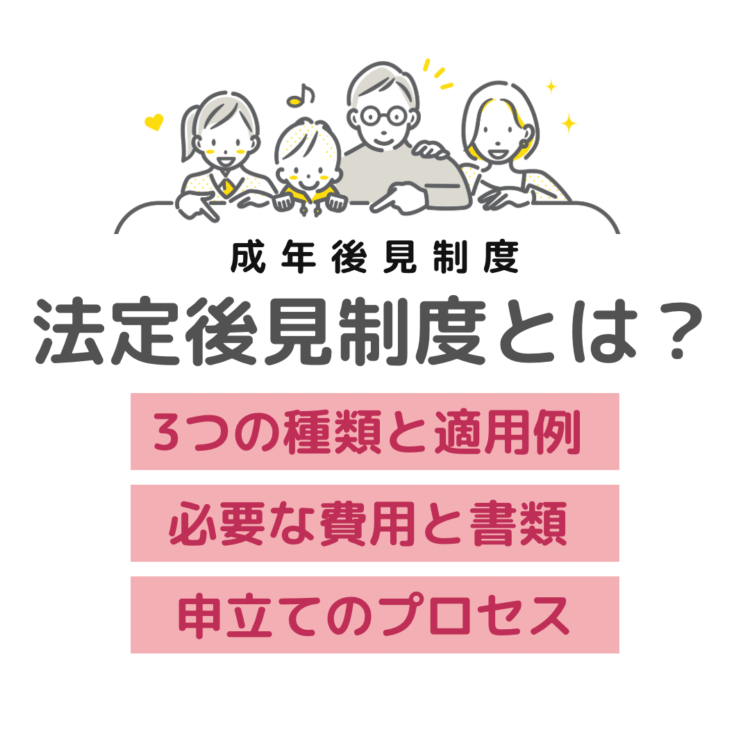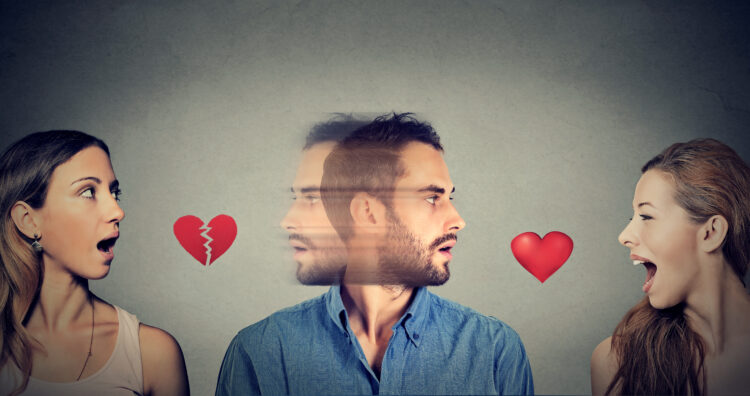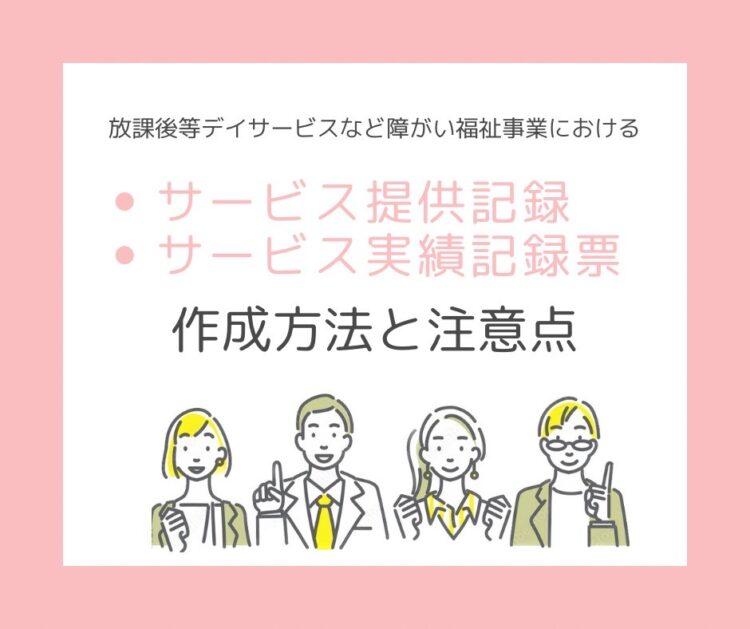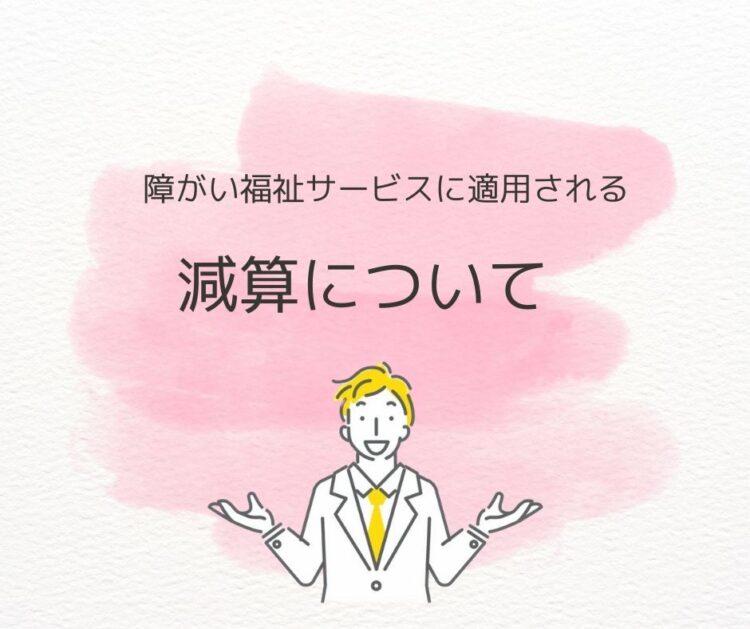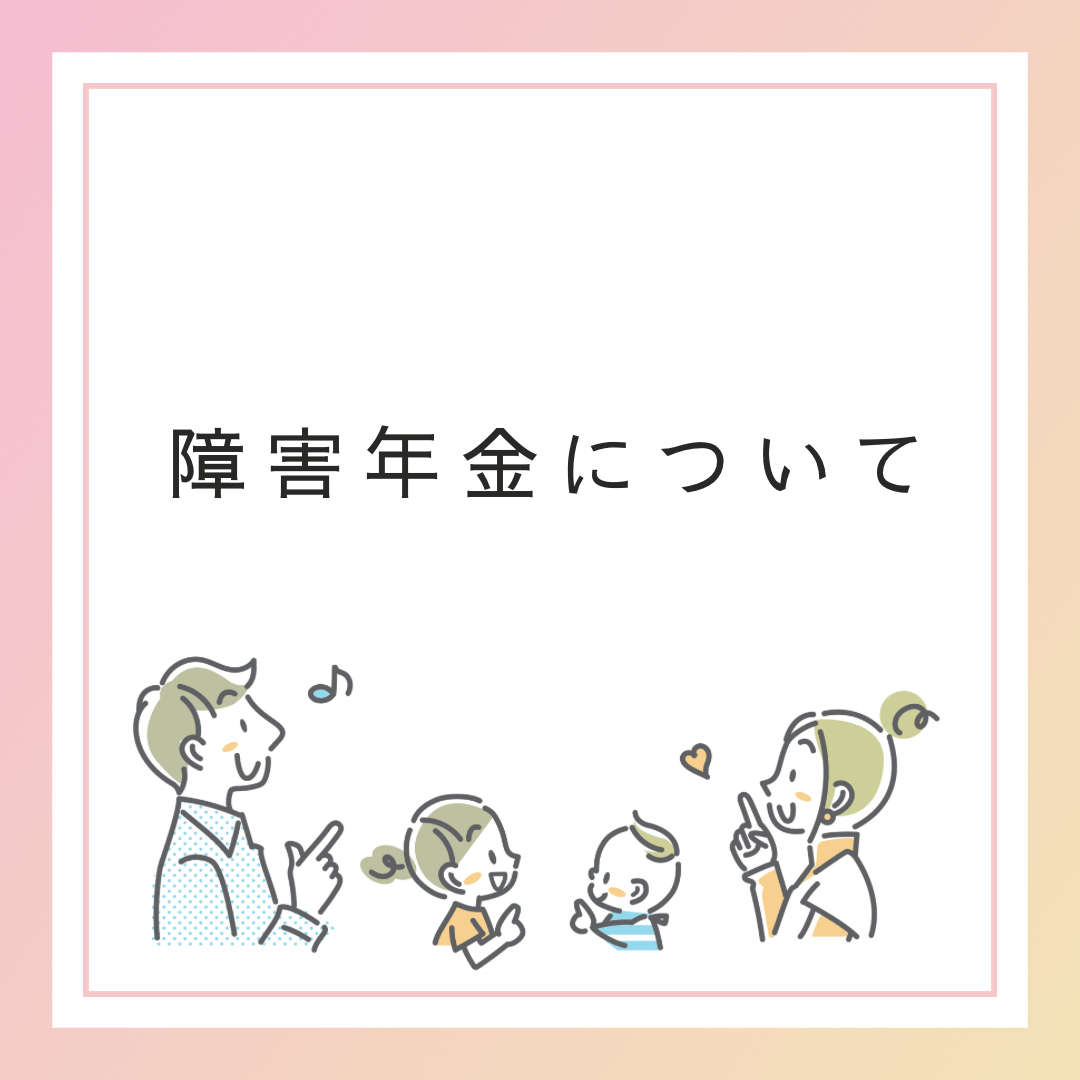
障害年金とは、病気やけがにより一定の障害状態になった場合に、その影響で働く能力が低下したり失われたりした人を経済的に支援するための公的年金制度です。この制度は、障害の程度に応じて支給され、生活の安定や再就職の支援を目的としています。日本における障害年金制度は、その人がどのような障害を持っているか、いつからその障害になったのか、そして国民年金や厚生年金保険に加入していたかどうかなど、さまざまな条件を満たす必要があります。今回は、障害年金について、その基礎から応用まで、誰にでも理解しやすいように解説していきましょう。
目次
障害年金ってなに?
病気や怪我で困っている時に助けになるお金
障害年金とは、病気や怪我で日常の活動や仕事に困るようになった人がもらえるお金のことです。この年金をもらうには、いくつかのルールがあるので、それを満たさなければなりません。
若い人でももらえます
年金はお年寄りだけのものと思われがちですが、それは違います。もし病気や怪我で仕事ができなくなったら、生活を守るために年金が出ます。公的な年金には3つの種類がありますが、障害年金は働いている年齢の人ももらうことができます。20歳から65歳になる前日まで申請が可能です。
年金の種類と内容
| 年金の種類 | 内容 |
|---|---|
| 老齢年金 | 年をとった時の生活を支えるための給付金 |
| 遺族年金 | 家族を失った後の家族の経済的支援のための給付金 |
| 障害年金 | 病気や怪我で労働が困難になった時の給付金 |
ほとんどの病気や怪我が対象です
障害年金は、交通事故で怪我をした人や、生まれつきの障害がある人だけでなく、精神疾患や発達障害、がんや難病、糖尿病など、たいていの病気や怪我が対象になります。
障害者手帳がなくても大丈夫
障害者手帳を持っていない人でも障害年金をもらえます。なぜなら、障害者手帳と障害年金は違う制度で、判断する方法も違うからです。障害年金をもらっている人の中には、障害者手帳を持っていない人もたくさんいます。
| 手帳の種類 | 判定方法 | 備考 |
|---|---|---|
| 身体障害者手帳 | 障害の程度により1級から7級まであります。 | 一度障害が確定すると、基本的に更新の必要はありません。 |
| 療育手帳 | IQ(知能指数)で判断します。 | 重いものから軽いものまで4つの段階があります。地域によって「愛の手帳」「みどりの手帳」などとも呼ばれます。成人後は基本的に再認定は不要です。 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 日常生活や仕事への影響度合いで1級から3級まであります。 | 障害年金とは別の制度であり、同じ病気で年金を受給できない場合でも手帳を受け取ることが可能です。基本的に2年ごとに更新が必要です。 |
たとえば、人工透析をしている人の場合、身体障害者手帳では1級に分類されることがありますが、障害年金では2級とされることもあります。「手帳が2級だから年金も2級」「障害がとても重ければ年金は1級」とは必ずしも一致しないのです。障害者手帳と障害年金が同じ等級であることもあれば、異なる場合もあります。障害者手帳の有無や等級は、障害年金を審査する時の一つの手がかりにはなりますが、決め手ではないと考えてください。
働きながらでも障害年金をもらえる
障害年金は、仕事をしている人ももらうことが可能です。実際に、障害年金を受け取っている人の約3分の1は働いています。視覚や聴覚の障害、手足の障害のように外見に現れる障害を持つ人は、仕事をしていても障害年金を受けるのにほとんど影響がないとされています。しかし、精神障害や発達障害、がん、内科的な病気など、体の内部の障害を持つ人は、障害の程度が軽いと見なされやすいため、働いていると障害年金の審査に影響が出ることがあります。だからこそ、障害年金を申請するときは、仕事の内容や職場での支援、仕事場での状況などを詳しく伝えることが重要です。すでに障害年金を受け取っている人が働き始めた場合でも、障害年金がすぐに停止されることはなく、次の更新時期までは継続してもらえます。障害者雇用で働いているなど、特定の支援を受けて働いている場合は、更新時にも引き続き支給が検討されます。
障害年金を受け取るためには申請が必要
障害年金をもらう資格があっても、自ら申請しなければ年金は支給されません。障害者手帳を持っていても自動的には年金が出るわけではなく、必ず申請手続きを行う必要があります。
障害年金の審査は書類で行われる
障害年金を受け取る資格があるかどうかは、提出された書類だけで決まります。介護保険の認定のように、市町村の職員が家を訪れて調査することはありません。審査は国が行い、具体的には日本年金機構の担当者や「認定医」と呼ばれる医師が行います。障害の状態を正確に伝えるためにも、必要な書類を完全に揃えることが大切です。
障害年金の二つのタイプとそれぞれの対象者
障害年金には二つのタイプが存在します。「障害基礎年金」と「障害厚生年金」です。これらを理解するには、「初診日」が重要です。この「初診日」とは、障害の原因となった病気やけがで最初に医師の診察を受けた日のことを指します。
| 年金の種類 | 対象となる人の条件 |
|---|---|
| 障害基礎年金 | – 初診日に国民年金に加入していた人 – 生まれつきの障害がある人 – 初診日が20歳未満の人 – 自営業者 – 無職の人 – 学生 – 配偶者に扶養されている人 |
| 障害厚生年金 | – 初診日に厚生年金保険に加入していた人 例:会社員 |
以前存在した公務員や私立学校職員向けの「障害共済年金」は、2015年10月に障害厚生年金へ統合されました。ただし、統合前に共済年金加入中だった人は、特例として「障害共済年金」の対象となります。
障害年金は障害の重度によって、重い方から順に1級、2級、3級に分類されます。1級が最も重い障害を指し、年金額も最も多くなります。
「障害基礎年金」は3級が存在せず、申請結果が3級となる場合は年金が支給されませんが、「障害厚生年金」では支給されます。「障害厚生年金」にはさらに「障害手当金」という一時金もあります。障害の程度の目安は以下の通りです。
障害の程度の目安
| 等級 | 障害の程度の目安 | 関連する年金 |
|---|---|---|
| 1級 | 他人の介助がなければ日常生活がほぼ送れない状態。入院や在宅介護が必要。 | 障害基礎年金、障害厚生年金 |
| 2級 | 他人の助けは常に必要ではないが、日常生活を送るのが困難。活動範囲が家や病院内に限られる。 | 障害基礎年金、障害厚生年金 |
| 3級 | 日常生活には支障が少ないが、仕事をすることに制限がある。 | 障害厚生年金のみ |
| 障害手当金 | 仕事に制限がある上で症状が安定している状態。 | 障害厚生年金のみ(一時金) |
障害年金を受給するための3つの条件
障害年金は、障害を持つだけではもらえません。受け取るためには、以下の3つの条件を全て満たす必要があります。
初診日条件
障害を引き起こした病気やケガを最初に診てもらった日に、あなたが年金制度に加入していることが必要です。
保険料支払い条件
初診日の前日までに、あなたが年金保険料をちゃんと支払っていた期間があること、または保険料の支払いが免除されていた期間があることが求められます。
障害の程度条件
障害の重さが、決められた基準に合っている必要があります。
「初診日条件」は特に重要です。この日がいつかによって、あなたが「障害基礎年金」をもらえるのか「障害厚生年金」をもらえるのかが変わってきます。また、「保険料支払い条件」を確認する期間もこの日によって決まります。
障害年金の金額とその仕組みについて
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2つのタイプがあり、支給される金額は、これらのタイプと障害の重さによって異なります。同じ障害等級でも、障害厚生年金の方が金額が高くなる傾向があります。
年金の金額は毎年4月から翌年3月までの1年間で定められ、年金は年に6回(2ヶ月ごと)支給されます。支給日は偶数月の15日ですが、もし15日が休日ならその直前の平日に振り込まれます。
障害基礎年金
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 年金額 | 1級:年間約100万円 2級:年間約80万円 |
| 子の加算 | 1人目・2人目:一人あたり年間約23万円 3人目以降:一人あたり年間約8万円 |
| 所得制限 | 20歳前に障害がある人は本人の所得に応じた制限がある |
障害厚生年金
| 障害厚生年金の要素 | 説明 |
|---|---|
| 年金額 | 給与の高さや勤務期間によって変動し、通常、給与が高く勤務期間が長い人の年金額が多い |
| 障害手当金 | 障害が固定した状態で働くことに制限がある人に対して、一時金として一度だけ支給される |
| 配偶者加給年金 | 障害等級が1級または2級の本人に配偶者がいる場合、年間約23万円が加算される |
障害の重さによる等級が1級、2級、3級(障害厚生年金のみ)とあり、1級と2級の場合、障害基礎年金も合わせて支給されます。それぞれの状況や条件により、支給額が異なるので、具体的な金額を知りたい場合は、年金機構などの公式情報を確認することが大切です。
障害年金の請求手続きの概要
障害年金を申請する際には、大きく分けて2つの方法があります。
障害認定日請求
| 障害認定日 | 申請できる期間 | 注意点 |
|---|---|---|
| 病気やケガの治療開始から1年半後、または治療無効が認められた日 | 障害認定日の翌月から | 遅れた場合、最大5年遡って受給の可能性あり |
事後重症請求
| 適用される日 | 申請できる期間 | 注意点 |
|---|---|---|
| 障害認定日後、65歳になるまでの間に病状が悪化した日 | 病状悪化後から65歳になるまで | 申請月の翌月から年金の支給開始 |
「65歳になるまで」という言葉は具体的には、65歳の誕生日の2日前までを指します。これらのルールを理解し、障害の状態に応じて適切なタイミングで申請することが大切です。
障害年金の請求(申請)手続きのおおまかな流れ
- 「初診日」の特定まずは障害の原因となった病気や怪我で初めて病院を訪れた日を確認します。
- 加入資格の確認年金事務所に行き、「保険料納付要件」を満たしているかどうかをチェックします。これには保険料が適切に納められていたかの確認が含まれます。
- 初診日の証明書類の取得初診日を証明する書類を集めます。
- 医師の診断書の取得担当医に障害の状態を診断してもらい、その診断書を書いてもらいます。
- 病歴・就労状況書の作成これまでの病歴や現在の就労状況に関する申立書を作成します。
- その他必要な書類の準備申請に必要なその他の書類を集めます。
- 請求書類の提出すべての必要書類を揃えたら、これらを年金事務所に提出し、請求手続きを行います。
障害年金の結果通知と振込のプロセス
結果通知の受領
障害年金の申請書類を提出してから、すべてがスムーズに進めば、約3~4ヶ月後に結果が郵送で届きます。ただし、書類に不備があるなどの理由で遅れることもあります。
年金の支給が決定した場合の通知
「年金証書」の到着
支給が決まると、「国民年金・厚生年金保険 年金証書」が送られてきます。これは、あなたが障害年金を受け取る権利がある日、障害の等級、次回の診断書を提出する時期などの重要な情報を含んでいます。
「年金振込通知書」の到着
年金証書を受け取ってから約2ヶ月以内に、年金振込通知書が送られてきます。ここには、最初の振込金額と振込日が記載されています。
年金の振込
振込通知書に記載された日付に、初回の障害年金が口座に振り込まれます。初回振込は、審査期間を考慮して複数月分が一度に入金されることが普通です。
全体の所要時間
書類準備に2~3ヶ月、結果が出るまでに3~4ヶ月、そして支給決定から実際の振込まで追加で約2ヶ月となるため、全プロセスには少なくとも6~7ヶ月かかります。
早めの行動の重要性
障害年金の申請は早めに行動することが大切です。申請が遅れると、支給開始時期が後ろにずれ、受け取れる金額が減少するリスクがあります。
障害年金の支給が決まらなかった場合の通知と対処法
もし障害年金の支給が決まらなかった場合、あなたは「不支給決定通知書」または「却下通知書」を受け取ります。これらの通知にはそれぞれ異なる意味があります。
| 不支給 | 障害の程度が障害年金を受けるための基準に達していないと判断された。 |
| 却下 | 「初診日」が明らかでない、または必要な保険料を支払っていないなど、障害の程度の審査前に請求が却下された。 |
もしこの結果に納得がいかなければ、あなたは異議を唱えることができます。その方法としては、次の3つがあります。
審査請求
決定通知を受け取ってから3か月以内に行う。この手続きでは、問題点を明らかにして、提出した書類を再検討してもらいます。
再請求
病状の変化があった場合など、障害年金の請求を一からやり直します。
審査請求と再請求の同時進行
上記1と2を同時に進めることも可能です。
審査請求の結果にも納得がいかない場合は、さらなる「再審査請求」が可能です。また、障害等級に関して不服があれば、「額改定請求」を検討することもできます。
不服申し立ては複雑な手続きであり、具体的な進め方はケースによって異なるため、専門家に相談することをおすすめします。詳細については、障害年金の不服申し立てに関するページを参照してください。
障害年金の受給後に知っておくべきこと
障害等級1~2級には保険料免除の特典がある
障害等級が1級または2級に認定された場合、国民年金の保険料が免除されます(これを「法定免除」と言います)。遡って障害年金が支給される場合は、その期間分のすでに払った保険料が戻ってくることもあります(還付)。ただし、「法定免除」を受けると将来の老齢基礎年金の額が減少することがあります。保険料の納付を続けることもでき、免除後も10年以内であれば過去にさかのぼって保険料を支払う(追納)ことも可能です。将来の年金受給額を考慮して、保険料の納付を続けるかどうか検討しましょう。厚生年金保険料には「法定免除」の制度は適用されません。
ほとんどの場合、定期的な更新手続きが求められる
障害年金の受給資格を維持するためには、1年から5年ごとの更新が必要です。更新時期が近づくと、「障害状態確認届」が送られてきます。これを医師に記入してもらい、誕生月の末日までに提出する必要があります。更新時には新たに書類を取り寄せる必要はありません。
更新時に障害等級が変わることがある
更新手続きを経て、障害等級が変更されることや、障害年金の支給が停止されることもあります。これは「障害状態確認届」の提出後、おおよそ3~4か月で通知されます。
更新の結果に不服があれば、申し立てが可能
更新の審査結果に納得がいかない場合、例えば病状が変わっていないのに障害等級が下がったり、支給が停止されたりしたときは、不服申し立てができます。
病状が悪化した場合は、等級の見直しを請求できる
もし受給中の障害が悪化した場合は、障害等級を見直す請求が可能です。手続きは障害年金の受給権を得てから基本的に1年後から行えますが、人工物を身体に入れた場合などは例外として早期に手続きできることもあります。「額改定請求書」は、障害状態の確認時にも提出できます。
支給停止中でも、状態が悪化すれば支給再開を求められる
支給が停止された際も、病状が悪化した場合は支給の再開を求めることができます。「支給停止事由消滅届」と診断書を提出して、再度審査を受けます。
他の年金を受給する際は、どの年金を受け取るか選ぶ必要がある
障害年金を受けている間に老齢年金や遺族年金を受給する資格が生じた場合、これらの年金から1つを選んで受給する必要があります。「一人一年金」が原則のため、同時に複数の年金を受け取ることはできませんが、65歳以上になると最も有利な組み合わせで受け取れる場合もあります。
まとめ
障害年金についてのご紹介を終えます。障害を持つことで生じる経済的な不安を和らげるための大切な制度であり、自分がもしもの時に備えて知っておくことは非常に重要です。障害年金の申請方法、受給資格、更新手続きなど、今後もこの情報が役立つかもしれませんので、頭の片隅に留めておいてください。もしもの時に備えて、またご自身や周りの人が必要とする時には、今回の情報が支援となることを願っています。何かご不明点があれば、専門家や日本年金機構に相談することをお勧めします。
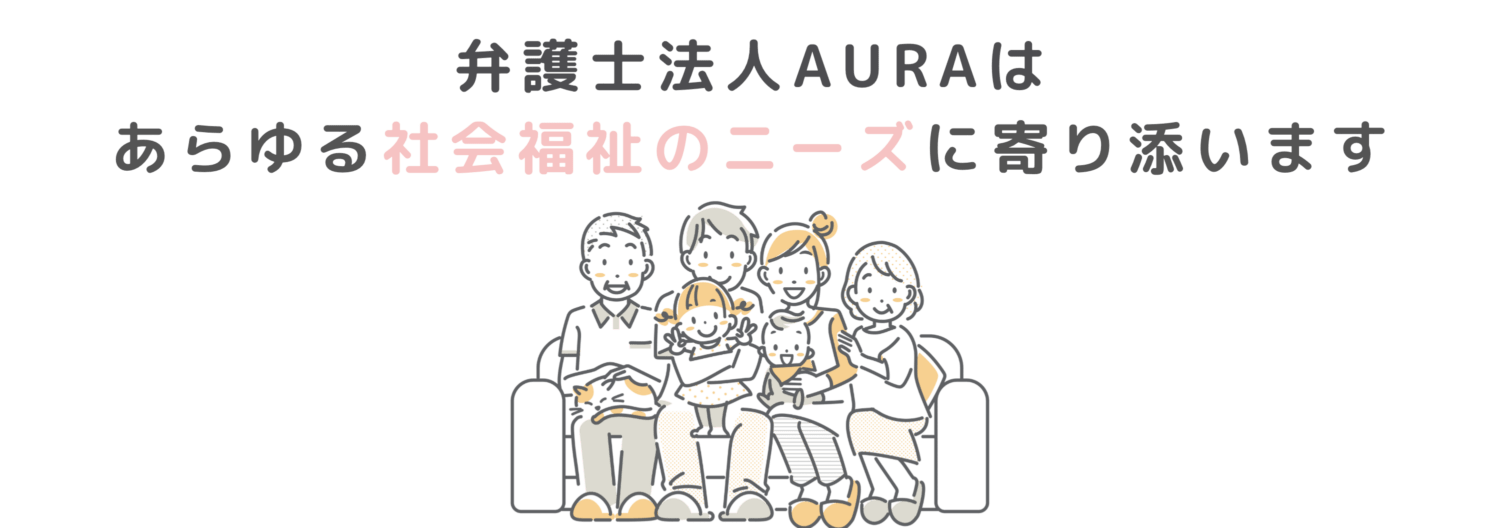
私たちは、幅広い福祉分野での経験を持ち、高齢者介護から障がい者や障がい児に関する悩み、一時保護から成年後見制度まで、多様な相談に対応しています。特に、ひとり親や母子家庭の支援において専門的なカウンセリングを提供し、あなたの心のケアや新しい生活への準備を支援します。必要に応じて、専門家の紹介や心理的なサポートも提供いたします。私たちは、あなたの隣に立ち、新たな未来に向けて共に歩むお手伝いをいたします。