児童発達支援及び放課後等デイサービスの開業支援

障がい福祉事業の開業支援について
ひとことに開業と言っても専門的な知識や経験が必要です。併せて開業までの時間がかかることや物件を検索することなどほかの作業も合わせるとかなりの労力がかかります。まず何を始めたらよいのか?どのような順序で進めたらよいのか?などのも含めて抱えている不安や疑問が多いでしょう。最近では多くの企業などがこの障がい福祉サービスの開業支援やコンサルに参入しており、参入診断で費用が掛かることも多くあります。そんな不安を解消するために弁護士法人AURAでは開業に関する手続きなどに関して各プラン別にオプションサービスに幅広いサービスをご用意しています。
事業参入前のご相談

障がいに関する基本的なこと
| 障がい者福祉とは |
|---|
| 障がい者福祉とは ・日本における障がい福祉事業について ・社会保障制度について(制度、サービスなど) ・障がいの種類(身体障がい、精神障がい、発達障がいなど) |
| マーケットの調査事業予測に関すること |
|---|
| ・障がい者児数 ・世帯数 ・年齢別人口分布 など |
| 事業予測 |
|---|
| ・売上予測や年間収支予算予測など |
開業時に必要な書類や手続き

開業するのに必要なこと
| 法人などの登記 |
|---|
| 事業運営には法人格が必要 ・合同会社 ・株式会社 ・NPO法人 など |
| 管轄行政相談対応 |
|---|
| 事前相談や協議、指定申請の流れなど |
| 事業指定申請書類 |
|---|
| ・事業指定申請書 作成 ・各種マニュアル 作成 ・帳票関係書類 作成 など |
| 物件検索、集客に関する相談 |
|---|
| 業務提携先 |
開業後も顧問先として

運営していくのに必要なこと
| 事務的サポート |
|---|
| ・各種契約書 ・税務関係書類 ・労務関係書類 ・社会保険関係 など |
| トラブル相談 |
|---|
| ・利用者間におけるトラブル ・経営側と従業員間におけるトラブル |
| 事業運営について |
|---|
| ・事業運営に関するご相談 ・集客に関するご相談 |
障がい福祉事業を始める前に知っておくべきこと
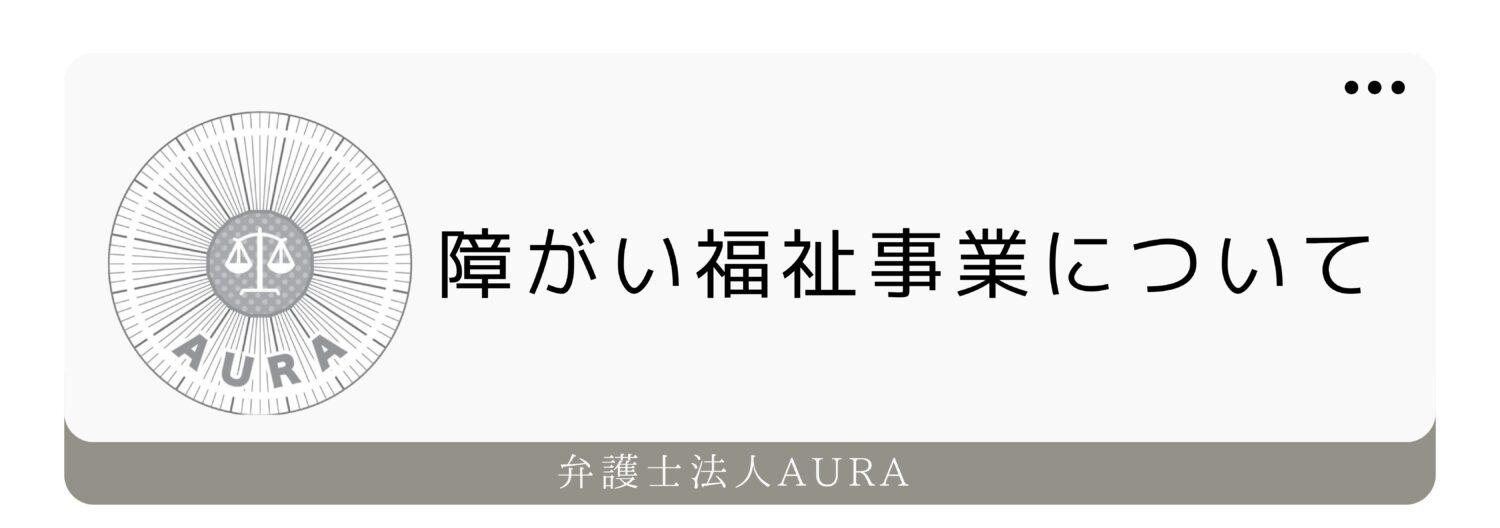
障がい福祉事業は、法律に基づいて制度設計されています。障がい福祉事業とは、障がいのある人、特定の難病にある人が地域で生活を続けていけるように支援する事業(サービス)の事です。障がい福祉事業では、障がいのある人が個人として尊重され、共生する社会を実現することを目的としています。また、障がいのある人と事業者との対等な関係にあり、障がいのある人(保護者などを含む)が、サービスを選択し障がい福祉事業所と契約によりサービスを利用するしくみです。
障がい福祉事業の根拠となる法律は、「障害者の日常生活及び社愛生活を総合的に支援するための法律(以下、障害者総合支援法)」と「児童福祉法」です。そして障がい福祉事業をスタートさせるためには、障害者総合支援法や児童福祉法に基づく行政からの指定が必要です。
障害者総合支援法に基づくサービス
障害者総合支援法に基づくサービスは、障がい者が自立した日常生活を送ることができるよう、支援を行うものです。具体的には、生活支援や就労支援、福祉用具の貸与や設置、通所支援、自立支援などがあります。これらのサービスは、障がいの種類や程度に応じて、必要な支援を提供します。また、地域に根差した支援を重視し、障がい者が地域社会に参加できるような取り組みも行われています。
訪問サービス

障がいを持つ人々が自宅や施設で生活する際に必要な支援を、訪問スタッフが提供するサービスのことです。訪問系サービスは、障がいを持つ人々が自宅で過ごし、自立した生活を送ることを支援するため、地域に密着したサービスとして展開されています。訪問スタッフは、個人のニーズに合わせたカスタマイズされた支援を提供することが求められます。
日中活動サービス

障がいを持つ人々が日中に活動する場を提供し、社会参加や自立支援などを促すサービスのことです。日中活動系サービスは、障がいを持つ人々が日中の時間を有意義に過ごすためのサービスであり、社会参加や自立支援の一助として展開されています。障がいを持つ人々が、より豊かな生活を送るための支援を提供することが目的となっています。
施設サービスと居宅サービス

障がいを持つ人々が生活するための施設を提供し、生活や介護などのサポートを行うサービスのこと。施設系サービスは、障がいを持つ人々が生活するための場やサポートを提供することで、社会参加や自立支援を促すサービスであり、地域に密着したサービスとして展開されています。居宅系サービスは、障がいを持つ人々が自宅で自立した生活を送ることを支援するためのサービスであり、地域に密着したサービスとして展開されています。障がいを持つ人々が、より豊かな生活を送るための支援を提供することが目的となっています。
訓練・就労サービス

障がいを持つ人々が社会的な役割を果たすために必要な能力を身につける訓練や、就労支援を行うサービスのことです。訓練や就労系サービスは、障がいを持つ人々が自立した社会生活を送るために、社会参加の一助となるサービスです。障がいを持つ人々が、自分の能力やスキルを活かして、自立した生活を送ることができるように支援することが目的となっています。
相談支援サービス

障がいを持つ人々やその家族が抱える問題について、専門の相談員が支援するサービスのことです。相談支援系サービスは、障がいを持つ人々やその家族が抱える問題を解決するために必要なサポートを提供するサービスであり、地域に密着したサービスとして展開されています。障がいを持つ人々が、より豊かな生活を送るための支援を提供することが目的となっています。
児童福祉法に基づくサービス
児童福祉法に基づく障害児支援サービスは、障がいを持つ児童やその家族が支援を受けるためのサービスです。具体的には、訪問支援や通所支援、放課後等デイサービス、就労支援、移行支援などがあります。これらのサービスは、児童の発達段階や障がいの程度に合わせて、必要な支援を提供します。また、地域に根差した支援を重視し、児童が地域社会に参加できるような取り組みも行われています。
障がい児通所支援サービス

障がいを持つ児童が通所することで、生活能力の向上や社会性の発揮を促すサービスのことです。障がい児通所支援サービスは、障がいを持つ児童が、家庭や学校の外で、様々な経験をすることを支援するためのサービスです。児童の発達や社会性の発揮を促し、より豊かな生活を送るための支援を提供することが目的となっています。
障がい児入所系サービス

障がいを持つ児童が、一定期間を施設で過ごしながら、生活能力の向上や社会性の発揮を促すサービスのことです。障がい児入所系サービスは、障がいを持つ児童が、家庭や学校の外で、様々な経験をすることを支援するためのサービスです。児童の発達や社会性の発揮を促し、より豊かな生活を送るための支援を提供することが目的となっています。
相談支援サービス

障がいを持つ児童やその家族が抱える問題について、専門の相談員が支援するサービスのことです。障がい児相談支援サービスは、障がいを持つ児童やその家族が抱える問題を解決するために必要なサポートを提供するサービスであり、地域に密着したサービスとして展開されています。障がいを持つ児童やその家族が、より豊かな生活を送るための支援を提供することが目的となっています。
障がい福祉事業の開業・手続き・運営について
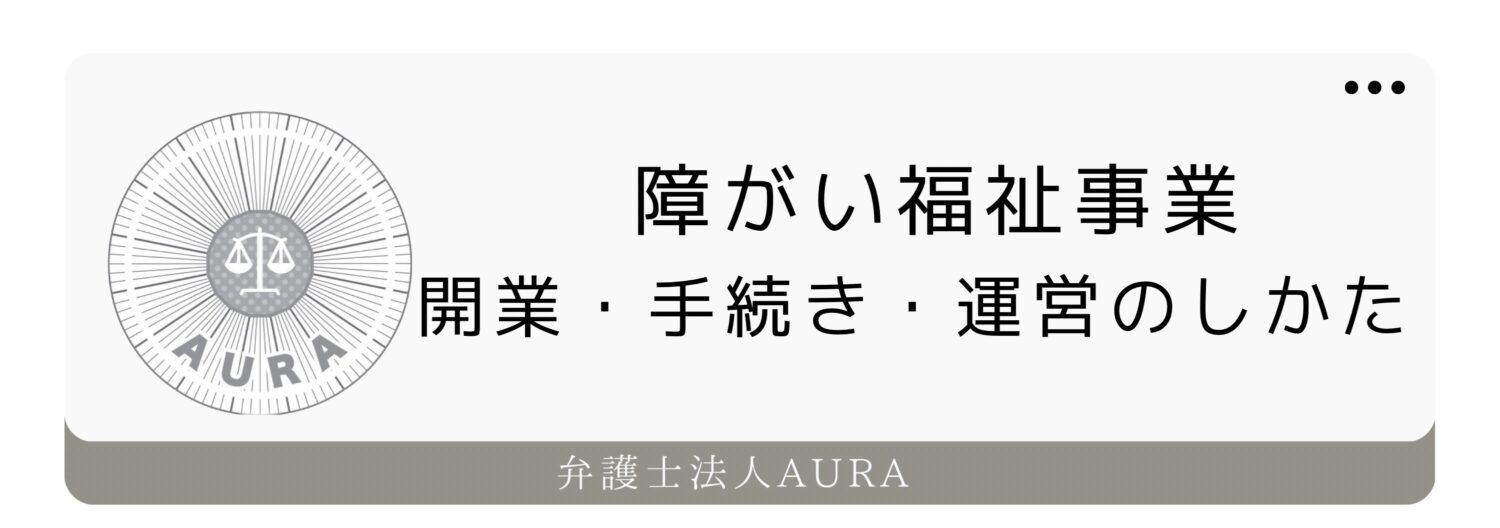
児童発達支援や放課後等デイサービスなど障がい福祉サービスの開業は専門的な知識が必要です。開業時に必要な手続きから申請書類、運営に必要な書類やサービス及び運営するにあたって知っておかなければならない必要事項を確認しましょう。
開業について

指定を担当している役所はどこであるの?指定権者の探し方、担当窓口、そして指定申請から事業開始までの流れについて。また指定を取るための法人格、人、物件、その他要件についてや指定を受けられない場合や多機能など(障がい者(大人)と障がい児の多機能型に関する例)についてまとめました。
指定申請に関する手続き

指定申請に必要となる書類についての解説、また決めておかなければならないことはもちろん、指定を受けた後の各種手続きや契約関係書類、各種マニュアルや規定についての作成方法や注意点などについて
加算・減産について

加算するための要件や代表的な加算項目についてやそのようなサービスがどのような減算の適用となるのかについて
適正運用について

障がい福祉事業の4つの原則についてや様々な基準の遵守、法令上の適正な事業運営、そのために必要な書類の準備、作成、請求について。虐待防止の重要性や取り組ににあたるポイントの解説。また適正な運営が行われているのか実地指導や監査、監査後の対応について
放課後等デイサービスを開業するための条件
では実際に、事業者としてサービスを提供するとなったとき、以下4つの基準を満たして認可指定を受ける必要があります。これらの基準は具体的にどういったものなのか、順番に説明をしていきます。

- 法人であること
- 人員に関する基準
- 設備に関する基準
- 運営に関する基準
法人格であること

放課後等デイサービスを新規開設するには法人を設立しなければなりません。法人には株式会社・合同会社・NPO法人などいくつか種類があり、それぞれメリット・デメリットが異なるのでよく検討して決めましょう。
- 株式会社
- 合同会社
- NPO法人 など
すでに法人格を持っている場合は、児童福祉法に基づき児童発達支援事業を行う旨を事業目的に記載し、定款の変更手続きが必要です
人員に関する基準

開業の時点で以下の職種・人数を確保する必要があります。利用者の数によって必要なスタッフ数が変わってくるので注意しましょう。機能訓練担当職員は必須ではなく、機能訓練を行う場合のみ配置が必要となります。
- 管理者
- 児童発達支援管理責任者
- 児童指導員又は保育士
- 機能訓練担当職員
放課後等デイサービスの人員基準(10人以下)は、次の人員(従業員)を指定する人数(配置)を確保しておくことが必要です。
設備に関する基準

設備に関する基準に関しては、以下の要件を満たしている必要があります。
- 指導訓練室
- 事務室
- 相談室
- 洗面台、トイレなど
事業の運営を行うために必要な広さを有する専用区画について
指導訓練室
- 指定申請先によって、障がい児1人当たりの床面積が決まっている
- プレイルームとして子どもたちが過ごす場所で、自治体ごとに広さの指定がある
事務室
- 職員、設備備品が収容できる広さを確保すること。
- 職員と備品を配置するための事務専用のスペース
相談室
- 相談内容が漏れないよう、遮蔽物などを設置して配慮したもの
- プライバシーに配慮できる空間にすること
トイレ・洗面台
- 衛生面の配慮が必要となる。
- トイレの手洗いと洗面所は別にして、石鹸・ペーパータオルの設置が必要
設備および器材について
- サービス提供に必要な設備及び備品(指導訓練室には、訓練に必要な機械器具等を完備すること)
- 手指洗浄、感染症予防のための設備及び備品
この他にも横になって休憩できる静養室があると望ましいとされています。上記の設備を整えられるような物件を探しましょう。
運営に関する基準
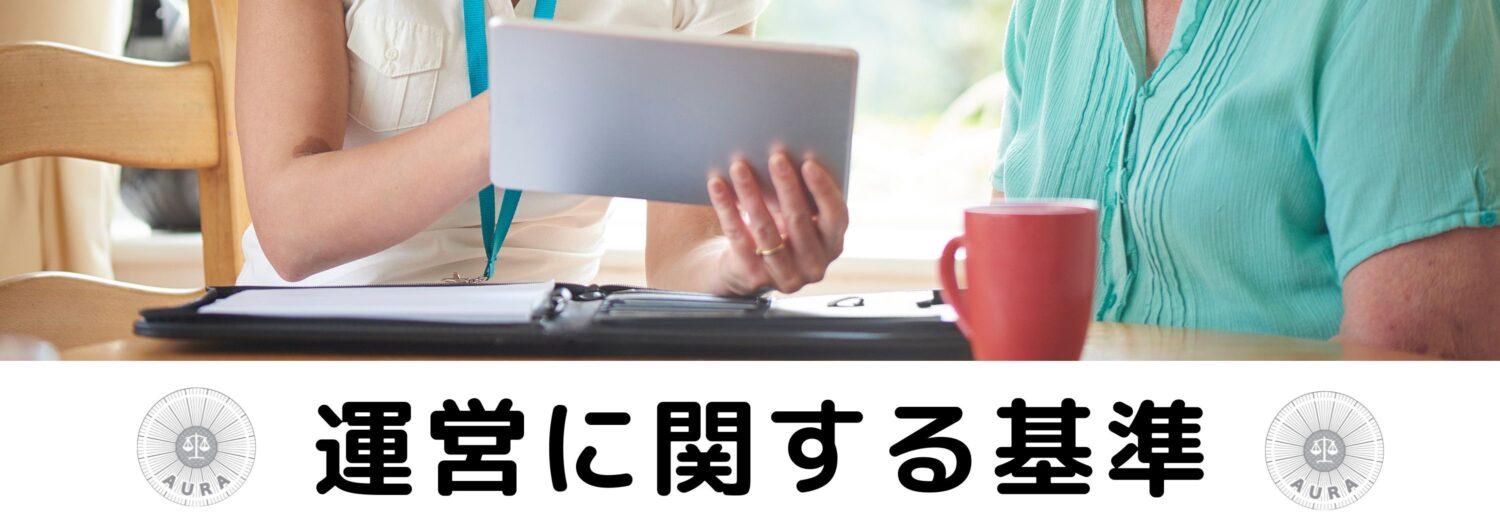
運営に関する基準を基に、事業所ごとに運営規程を定め、その概要を利用者の方に重要事項説明書を使って説明する必要があります。施設運営に関しては、以下のような基準が定められています。
- 利用定員が10名以上であること
- 放課後等デイサービスの個別支援計画が作成されていること
- サービス内容や手続きの説明と同意
- サービス利用者の指導、訓練等の実施
- 負担額の受領
- 利用者・家族からの相談や援助
- 利用者管理台帳の準備
- 利用者の病状急変時等における緊急体制の整備
弁護士法人AURAが開業支援でできること
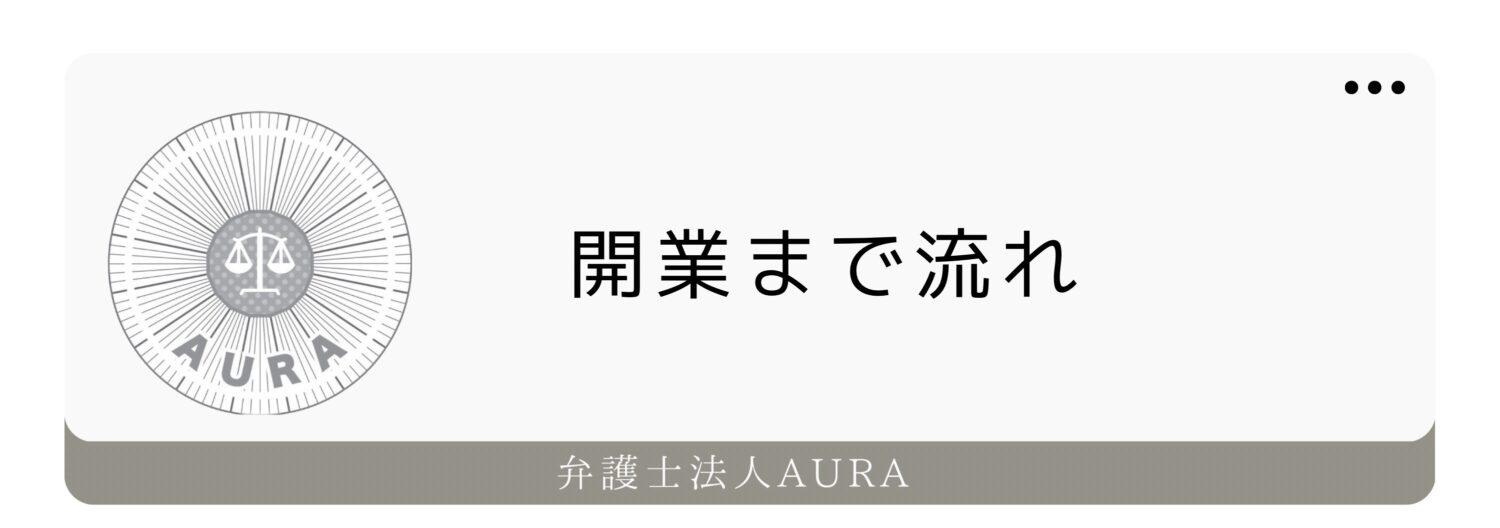
- 児童発達支援・放課後デイサービスなど障がい福祉事業開業についてお問合せ下さい
・ご希望地域などの総量規制などを確認など含めた商圏調査を実施
・物件の検索と事業所のレイアウト提案
・開業にあたる必要書類や今後の流れについてご説明
・収支モデルの作成 など
放課後等デイサービスなど障がい福祉サービス事業に関する様々なご相談に応じます。併せて開業にあたるご説明も行います。わからないことはここでしっかりと明確にしておきましょう。
- 開業支援サポート
・資金調達(銀行融資や日本政策金融公庫など)の実施
・物件契約
・事業指定申請、関連書類の作成
・指定権者(管轄行政相談対応)
実際の開業にあたる資金調達や必要書類の作成、行政対応などを一緒に行います。
- 運営におけるサポートの準備
・集客方法やホームページ作成
・人材募集や教育支援
・雇用契約書等準備
・各種療育プログラムの作成
運営における集客や人材募集、各種療育プログラムなどを業務提携先と共にサポート致します。
- 開業後の運営サポート
開業後の運営サポートなどについても業務提携先を含めサポート体制を用意。障がい福祉サービスにおける適切なサービス提供が実現できるとともに、事業者や利用者にとっても安心・安全な環境が確保されます。しかし、法律や規則の改正や変更、新たな問題の発生などに対応するために、障がい福祉サービスには常に最新の情報や知識など業務提携先と共にサポート致します。(別途支援サポート契約)

初期費用ってどのくらい必要なの?

初期費用としてかかるのは主に以下のようなものです。
放課後等デイサービスの初期費用
- 法人の設立費用
- 不動産に関する費用
- 施設の保険費用
- 職員の求人広告費用
- 集客の費用
- 備品の購入費用
- 送迎車の購入費用
それぞれの目安となる金額を詳しく解説します。
法人の設立費用
先述した通り、放課後等デイサービスを立ち上げるには法人を設立する必要があります。一般的には株式会社か合同会社として設立されるケースが多いです。株式会社は最もメジャーな会社形態であり信用を得やすいため、集客や融資の際に有利になるでしょう。また、株式による資金調達も可能です。
株式会社を設立する際は、登録免許税として約15万円・定款認証代として約5万円がかかるので合計で20万円ほど必要になります。設立までには1ヶ月近くかかると見込んでおきましょう。
合同会社の場合の費用は約6万円で済み、3日程度で設立が可能です。しかし株式会社よりも認知度が低く、社会的な信用が高いとは言い切れないため、職員採用の際などに不利になる可能性もあります。
| 概要 | 金額 |
|---|---|
| 法人等設立費用 | 60,000円~200,000円 |
| 資本金 | |
| 登録免許税 | ~149,800円 |
| その他雑費 | 10,000円~ |
不動産の賃貸費用

地域によって不動産の賃貸費用は大きく異なりますが、支払い続けることを考えると都市部では20万円程度、その他の地域では15万円ほどに収めておくのがおすすめです。
開業時には敷金・礼金や不動産会社への仲介手数料、準備期間の家賃や内装費用も必要になるため、総額で300万円以上かかることもあります。
運よく居抜き物件が見つかれば内装費用はかかりませんが、そうでない場合は内装工事のために開業の2ヶ月程度前から賃貸契約を結んで家賃を支払わなければなりません。
| 概要 |
|---|
| 保証金(敷金) |
| 礼金 |
| 仲介手数料 |
| 前家賃 |
| 共益費 |
施設の保険費用

施設賠償保険として約6万円・火災保険として2万円ほどかかります。他にも、教室に通う子どものケガや事故に備えた保険や、施設向けに用意された損害賠償保険などへの加入も必要に応じて検討しましょう。
賠償責任の保険への加入の規則はありませんが、トラブルを完全に防ぐのは難しいため、立ち上げと同時に加入しておくことをおすすめします。
| 補償種類 |
|---|
| 施設損害補償 |
| 業務遂行損害補償 |
| 生産物損害補償 |
| 仕事の結果損害補償 |
| 受託財物損害補償 |
| 支援事業損害補償 |
| 人格権侵害補償 |
送迎車の購入費用

送迎サービスを行う場合は、車両を準備しなければなりません。利用者の人数や送迎の範囲によって異なりますが、一般的に車両は2・3台必要だと言われています。車両は1台あたり50万円〜500万円ほどで、条件によって費用は大きく変動します。自動車保険に加入することも考慮すると、総額350万円以上はかかると見込んでおきましょう。
児童発達支援管理責任者や児童指導員・保育士のスタッフは配置が義務付けられており、人数の基準も細かく定められています。求人広告媒体で募集する場合、人員が集まるまでの日数にもよりますが50万円ほどかかると見込んでおきましょう。
ただし、身内や知り合いで人員を揃えられる場合は、広告を出さずに済むので費用はかかりません。何名か魅力的な人材を集められたら、周囲にスタッフになれそうな人がいないか聞いてもらい、人員を集めていくのも一つの手段です。
備品の購入費用

適切な支援を行いながら安全に運営していくためには、教室の設備をしっかりと整える必要があります。主に購入しなければならない備品は以下のようなものです。これらを揃えるには100万円以上かかると見込んでおきましょう。教室の規模が大きいほどその分多く購入しなければならないため、さらに費用がかかります。安く購入できる店や譲ってもらえるものなどがあれば活用するのも良いでしょう。
また、教室の規模によって必要な消防設備が変わってきますが、上記の備品以外に火災時の対策も必要です。誘導灯や消火器は約15万円・自動火災報知設備は100万円以上かかることもあります。
職員の求人広告費

児童発達支援管理責任者や児童指導員・保育士のスタッフは配置が義務付けられており、人数の基準も細かく定められています。求人広告媒体で募集する場合、人員が集まるまでの日数にもよりますが50万円ほどかかると見込んでおきましょう。ただし、身内や知り合いで人員を揃えられる場合は、広告を出さずに済むので費用はかかりません。何名か魅力的な人材を集められたら、周囲にスタッフになれそうな人がいないか聞いてもらい、人員を集めていくのも一つの手段です。
運営資金ってどのくらい必要なの?

続いて運転資金について詳しい内容を確認していきましょう。
1ヶ月に必要な運転資金の目安は以下の通りです。家賃17万円の賃貸物件で開業し、平日のみの営業で利用者定員が10名。スタッフは管理者兼児童発達支援管理責任者1名・児童指導員2名の合計3名の施設を例とします。
例に挙げた施設の場合、1ヶ月あたり1,085,000円の運転資金が必要になります。
経営が軌道に乗るまでの3ヶ月間の運転資金を用意しておくと考えると、1,085,000円×3ヶ月=3,255,000円ほどは準備しておくと安心です。
| 家賃 | 17万円 |
| 光熱費 | 15000円 |
| 人件費 | 80万円 |
| その他 | 10万円 |
| 合計 | 1,085,000円 |
開業スケジュール
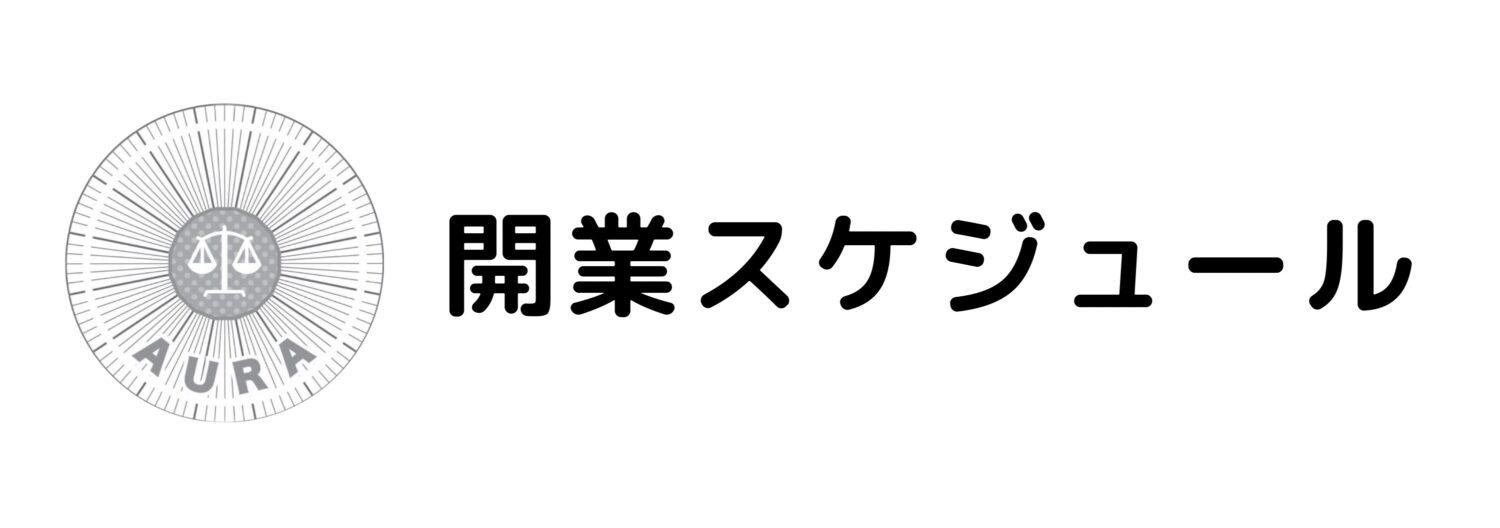
放課後等デイサービスを開業するためには、準備期間を含めると少なくとも半年から1年ほどかかると見込んでおきましょう。以下のようなスケジュールで準備を進めます。法人の設立や資金調達は申請から受理までに時間がかかるので、余裕を持って準備に取りかかりましょう。
【放課後等デイサービスの開業スケジュール】
- 事業内容の検討・指定基準の確認
- 法人の設立
- 行政機関との事前協議
- 物件の準備・内装工事・備品設置
- 申請書類の作成・提出
- 管理者の研修・障がい児支援事業者の指定
- 運営前の最終準備
- 事業の開始
児童発達支援・放課後等デイサービスなどの指定申請の手順について
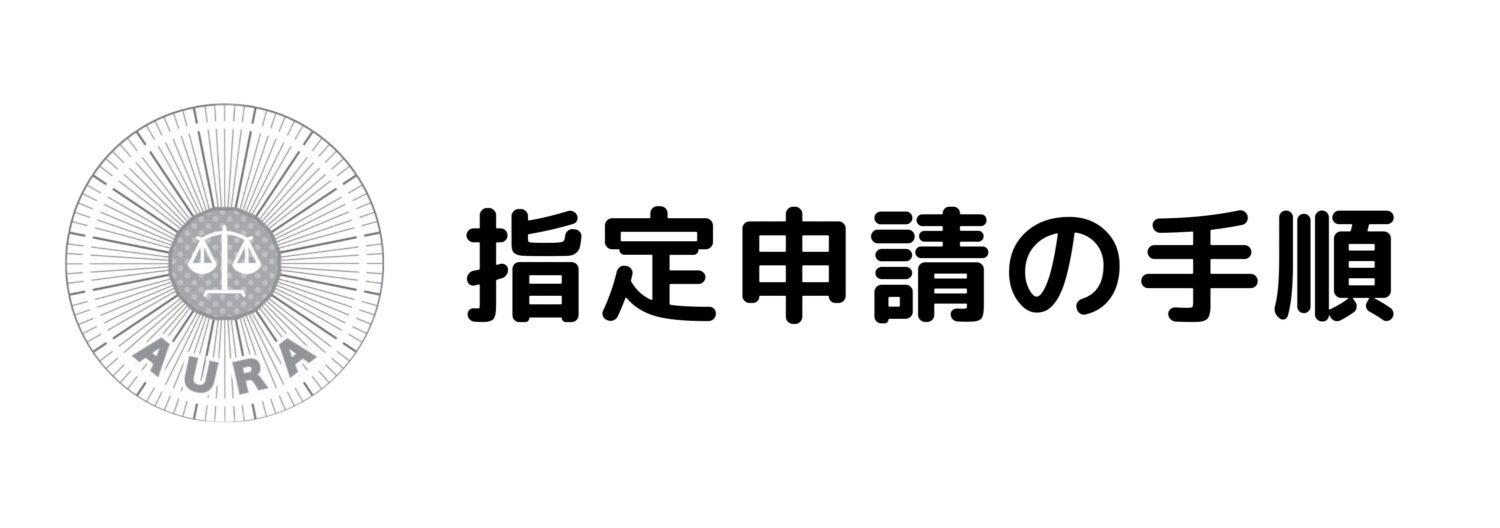
まずは児童発達支援・放課後等デイサービスなどの指定申請の手順についてです。指定申請の流れは次の通りになります。開業における注意点は次の通りです。
- 都道府県や市町村によって申請の仕方が異なる場合があります。事前に確認しておきましょう。
- 申請から指定を受けるまでに1カ月以上かかります。余裕を持って、開業計画を立てましょう。
- 定款に「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」と記載する必要があります。
- 資格者の確保には苦労する場合がありますが、名義貸しなどの違法行為は厳禁です。
| 指定申請の手順 |
|---|
| ①事前相談 |
| ②申請書類の提出 |
| ③申請書類の受理 |
| ④現地の確認 |
| ⑤指定通知書の送付 |
| ⑥事業者の指定 |
障がい福祉事業開業に関する現状とは
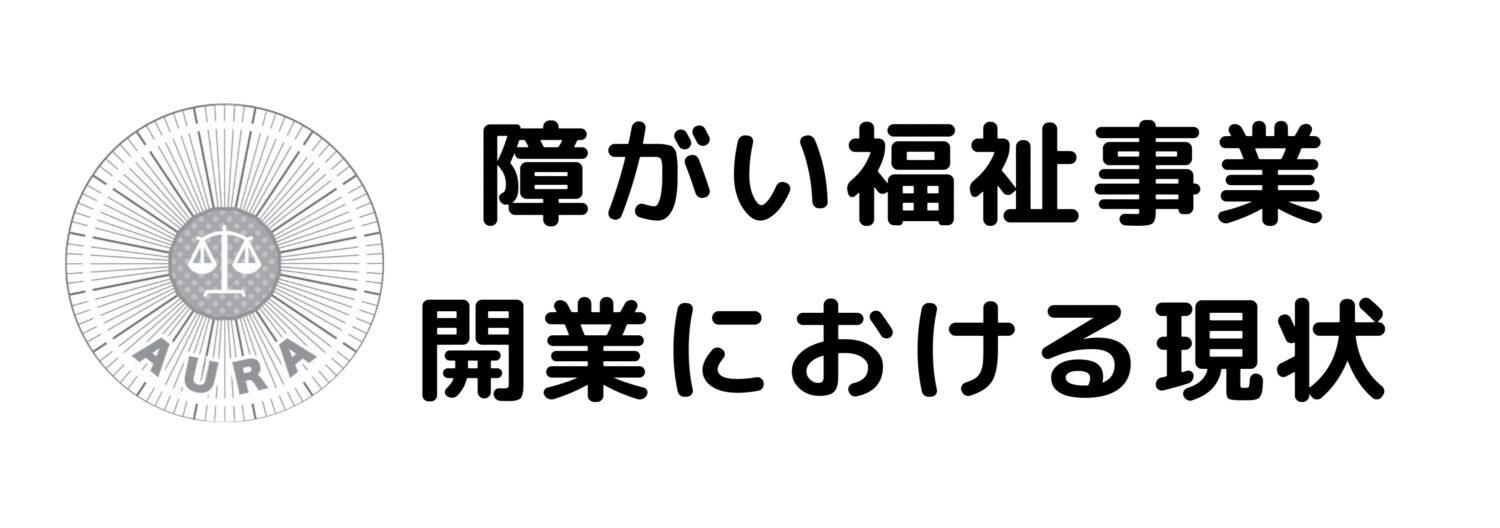
上記の基準を満たすことができて、ようやく開業の手続きが進められます。障害福祉事業にはどういった特徴があるのかや、施設の現状を以下にまとめました。
小資本で始められる
飲食店やコインランドリーのようなあ店舗ビジネスを立ち上げる場合、初期費用は1000万円以上かかります。放課後等デイサービスの場合、遊具や家具などの小資本から始められます。開業資金のみの場合、300~500万円くらいが相場です。開業においても、福祉事業の場合は国からの融資などが仕組みとして整っています。そのためサポートを活用しやすいという利点もあります。
オーナーが福祉の有資格者である必要はない
人員に関する基準に示したとおり、放課後等デイサービスに関して、福祉に関する有資格者でなければ始められないと思われがちです。ただ、施設のオーナーに関しては、ご自身と別に児発管や指導員の配置ができていれば資格を有している必要はありません。障がい児に対する直接的なサポートは福祉のプロである児発管に専任してもらうことをお勧めします。一方で、オーナーは障がい児が自立ができる仕組み作りや、スタッフが働きやすい環境作りを考えるなど、施設経営に専念すると良いと思います。その際はぜひ管理者さんとコミュニケーションを図り、良質な施設作りを進めてください。
他業種からでも開業しやすい
資格も必要なく、開業資金も比較的、低予算で始められるので、起業精神の強い方が成功しやすい分野となっております。また、障がいをもつ児童に対する直接的なサポートは福祉のプロである有資格者に専任してもらうことで、オーナーはサービス利用者が自立ができる仕組み作りや、スタッフが働きやすい環境作りを考えるなど、施設経営に専念する事ができます。
障がい児童の数に対し、受け入れる体制が追いついていない
先ほども少し触れましたが、年々知的障がい児の数は増加傾向にあるにも関わらずその障がい児たちを受け入れる施設が足りていないのが現状です。国もこの問題に対し、助成金や補助を導入するなどあらゆる施策を講じており、社会貢献性も高い事もあって、これから参入される事業者が増えて来る事が予測されています。放課後等デイサービスは社会貢献度も高く、6歳〜18歳と、長期間にわたって子どもの発達支援に携わることができます。さまざまな基準があり、大変な印象を受けられたかもしれませんが、開業については特別な資格を保有していなくてもできることですので、人員の確保と基本的な知識を備えることができれば、比較的早く開業に至ることができるのもポイントです。地域に根差し、子どもたちの自立を身近で見守り、サポートできる放課後等デイサービス。地域貢献や福祉に興味がある方にはぜひおすすめしたい事業です。
社会貢献ができる
学校や家庭とは異なる空間・時間・体験を通じ、子どもたちの自立を身近で見守りサポートすることができます。子どもたちの社会貢献を支援する事でその役割を果たす、社会的意義の大変高い事業です。
料金について
指定申請単独プラン

指定申請のみを行う単独のプランです。この内容は、現在障がい福祉事業を経営している事業所などで次の店舗を指定希望をする方です。指定後の相談は別途費用が掛かります。
料金
44万円(税込み)
| 内容 | 備考 | |
|---|---|---|
| 現地の調査と確認 | 1件 | 2件目以降、1件につき、30,000円(別途交通費、消費税) |
| 消防署への同行 | × | |
| サポート期間 | 契約から4ヵ月又は指定日の前日 | |
| 各種申請書類等 | ・利用契約書、重要事項説明書など書類 ・各種マニュアル ・帳票類 など | 別途、6万円+税/1件 |
| 処遇改善加算同時申請 | 特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算は含まれません | 別途、4万円+税 既に提出している計画書を基に作成 |
A プラン

指定申請のみを行う単独のプランです。この内容は、現在障がい福祉事業を経営している事業所などで次の店舗を指定希望をする方です。指定後の相談は別途費用が掛かります。
料金
66万円(税込み)
| 内容 | 備考 | |
|---|---|---|
| 現地の調査と確認 | 2件 | 3件目以降、1件につき、10,000円(別途交通費、消費税) |
| 消防署への同行 | 〇 | |
| サポート期間 | 契約から4ヵ月、指定後1カ月 | 電話又はWEB会議対応 |
| 各種申請書類等 | 2つまで無料 | 3つ目以降は5万円 |
| 処遇改善加算同時申請 | 特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算は含まれません | +2万円(既に提出している計画書を基に作成します) +4万円(新規で提出する場合) |
B プラン

初めて障がい福祉に取組まれる方の一般的なプランです。指定後も2か月対応
料金
110万円(税込み)
| 内容 | 備考 | |
|---|---|---|
| 現地の調査と確認 | 3件 | 4件目以降、別途交通費のみ |
| 消防署への同行 | 〇 | |
| サポート期間 | 契約から4ヵ月、指定後2カ月 | 電話又はWEB会議対応 |
| 各種申請書類等 | 4つまで無料 | 5つ目以降は2万円 |
| 処遇改善加算同時申請 | 特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算は含まれません | +2万円(既に提出している計画書を基に作成します) +4万円(新規で提出する場合) |
C プラン

初めて障がい福祉事業を開業する人向けのトータルサポートプランです。指定後も3か月対応
料金
132万円(税込み)
| 内容 | 備考 | |
|---|---|---|
| 現地の調査と確認 | 5件 | 4件目以降、別途交通費のみ |
| 消防署への同行 | 〇 | |
| サポート期間 | 契約から4ヵ月、指定後3カ月 | 月1回訪問、電話相談又はWEB会議対応 |
| 各種申請書類等 | 〇 | 追加料金なし |
| 処遇改善加算同時申請 | 〇 | 追加料金なし |
弁護士法人AURAでは、障がい福祉事業(児童発達支援・放課後等デイサービス・相談支援事業所など)、開業に関する各種オプションメニューをご用意したサポートを行っています。お問い合わせやご相談料は無料です。

| 大手企業開業コンサル | FC型開業コンサル | |
|---|---|---|
| サービス提供期間 | 開業準備~運営まで | 開業準備まで |
| 費用 ・初期費用 ・ランニング費用 | ・350万円 ・2万円~ | ・340万円 ・ロイヤリティ:売上10%~や固定費+3% |
| 申請手続き | △ | △ |
| 施設環境設備 | 〇 | 〇 |
| 人材採用支援 | 〇 | 〇 |
| 物件探索 | × | △ |
| 販売促進 | 〇 | 〇 |
| 請求代行 | △ | 〇 |
| 行政実地調査立ち合い | × | △ |
| 人材育成 | 〇 | 〇 |